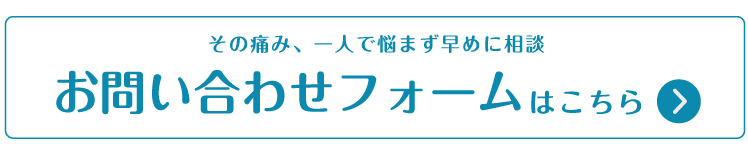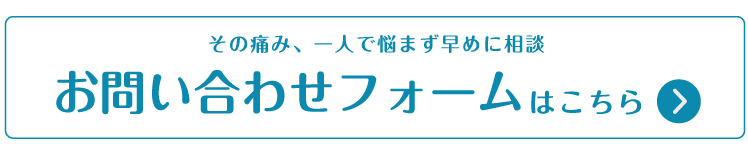後頭神経痛

腓骨神経麻痺とは
腓骨神経麻痺(ひこつしんけいまひ)は、膝の外側を通って足先まで達する腓骨神経が障害されることによって起こる神経障害です。この神経は坐骨神経から分岐し、膝の外側にある腓骨頭の後ろを巻きつくように走行しています。解剖学的に、この部位は神経の移動性が乏しく、骨と皮膚・皮下組織の間に神経が存在するため、外部からの圧迫により容易に麻痺が生じやすい特徴があります。
腓骨神経は主に足首を上げる筋肉(前脛骨筋)や足の指を上げる筋肉(長短母趾伸筋や長短趾伸筋)を支配しているため、麻痺が生じると足首や足指を上げる動作が困難になります。また、下腿外側から足の甲にかけての感覚も司っているため、感覚障害も併発します。
腓骨神経麻痺の症状・病態
運動障害
腓骨神経麻痺の最も特徴的な症状は下垂足(ドロップフット)です。これは足首(足関節)を背屈させることができなくなり、足が垂れ下がった状態になることを指します。これにより以下のような問題が生じます。
・足の指(第5趾を除く)を上に持ち上げることが困難になる・歩行時につま先が地面に引っかかりやすくなり、つまずきやすくなる
・階段の上り下りや不整地での歩行が特に困難になる
感覚障害
感覚障害としては、下腿の外側から足背にかけての感覚低下やしびれが現れます。また、第5趾(小指)を除いた足指背側の感覚異常も生じ、触った感じが鈍くなる(触覚鈍麻)こともあります。これらの感覚障害は日常生活での危険察知能力も低下させることがあります。
日常生活への影響
腓骨神経麻痺は日常生活に様々な影響を及ぼします。靴下や靴を履く動作が困難になり、履く際には座って片手で足を支える必要が出てきます。正座ができなくなったり、和式トイレの使用が困難になることもあります。また、スリッパやサンダルが脱げやすくなるため、転倒リスクが高まります。
長期間放置すると、下腿の筋肉の萎縮や拘縮が生じ、血流障害による症状の悪化や、廃用性萎縮による機能低下なども懸念されます。特に重度の場合は、移動時に杖などの補助具が必要になることもあり、生活の質が著しく低下する可能性があります。
腓骨神経麻痺の原因
腓骨神経麻痺の原因は多岐にわたりますが、主なものとして以下が挙げられます。
外部からの圧迫
最も一般的な原因は外部からの圧迫です。
・下肢の牽引などで仰向けに寝た姿勢が続いた場合・膝周辺の骨折などでギプス固定をしているとき
・手術後につま先が外に向いたままで長時間寝ている場合
・長時間の正座や足組みなどの習慣的な姿勢
圧迫により神経の血流が阻害され、一時的な麻痺が生じることがあります。圧迫が長時間続くと、永続的な障害に発展する可能性もあります。
外傷性要因
外傷による腓骨神経麻痺も少なくありません。特に交通事故による以下のような外傷は注意が必要です。
・交通事故で膝をダッシュボードにぶつけるなどの膝周辺の外傷・腓骨頭骨折
・膝関節の前・後十字靱帯損傷
・脛骨顆部のプラトー骨折や遠位端骨折などの下腿骨の骨折
・足関節周辺の内外果骨折
特に交通事故による腓骨神経断裂は、骨折がなくても発生することがあり、非可逆的な症状となる可能性が高いため、早期の診断と対応が重要です。
腫瘍性要因
腓骨頭部周辺に発生する腫瘤も圧迫の原因となります。
・ガングリオンなどの嚢胞性腫瘤・神経鞘から発生する神経鞘腫
・その他の腓骨神経に圧迫を与える腫瘍
これらの腫瘍性病変は、徐々に大きくなることで神経を圧迫し、進行性の神経症状を引き起こすことがあります。
その他の要因
・糖尿病に伴う末梢神経障害の一部として発症することがある・加齢に伴う神経変性
・特発性(明らかな原因なく発症するもの)
腓骨神経麻痺へのツボ・鍼灸治療
鍼灸治療は腓骨神経麻痺の症状改善に補助的な役割を果たすことがあります。
主要なツボ(経穴)
腓骨神経麻痺の治療に効果的とされるツボには以下のようなものがあります。
・陽陵泉(ようりょうせん):腓骨頭部の下方にあり、腓骨神経が通過する部位に位置する・足三里(あしさんり):膝の下、すねの外側にあるツボで、下肢の血流改善や神経機能の回復に効果がある
・絶骨(ぜっこつ):外くるぶしの上方にあり、足関節の機能改善に効果がある
・崑崙(こんろん):外くるぶしの後方にあり、足部の痛みやしびれの緩和に効果がある
鍼灸治療のアプローチ
鍼灸治療では、様々なアプローチを組み合わせて効果を高めます。腓骨頭周辺や麻痺した筋肉に直接鍼をする局所治療と、経絡理論に基づき関連する経絡上のツボを刺激する遠隔治療を併用することが多いです。また、低周波電気鍼を用いて麻痺した筋肉の収縮を促し、筋萎縮を予防する方法も効果的です。
これらの治療により、神経の再生促進、局所の血流改善、筋萎縮の予防、痛みやしびれの緩和、運動機能の回復補助などの効果が期待できます。ただし、鍼灸治療は補完的な治療法であり、医師による適切な診断と治療計画の下で行うべきです。また、神経の完全断裂などの重度の場合は、効果が限定的な場合があります。
腓骨神経麻痺への治療(鍼灸治療以外)
腓骨神経麻痺の治療は、原因や症状の重症度によって異なりますが、大きく保存的療法と手術療法に分けられます。
保存的療法
薬物療法
薬物療法では、神経の修復を促進するためのビタミンB12製剤や、神経周囲の炎症を抑えるための抗炎症薬が主に用いられます。痛みを伴う場合には鎮痛剤も処方されることがあります。これらの薬剤は、神経の回復環境を整える役割を果たします。
リハビリテーション
リハビリテーションは腓骨神経麻痺の機能回復に重要な役割を果たします。麻痺した筋肉(特に前脛骨筋や足趾伸筋群)の筋力増強訓練や、足関節の可動域制限を予防・改善するためのストレッチングが行われます。また、下垂足に対応した歩行パターンの習得を目指す歩行訓練も実施されます。
理学療法士の指導のもと、個々の症状や進行状況に合わせたプログラムが作成され、定期的に評価と調整が行われます。
物理療法
物理療法としては、麻痺した筋肉に電気刺激を与える電気刺激療法が広く用いられています。これにより筋収縮を促し、筋萎縮を予防する効果が期待できます。また、超音波療法や温熱療法なども、局所の血流を改善し神経の修復を促進する目的で行われることがあります。
装具療法
足関節を固定し歩行時のつま先の引っかかりを防ぐための装具も重要な治療法です。代表的なものには以下があります。
・短下肢装具(AFO):足関節を機能的な位置で固定する装具・オルトップ:プラスチック製の軽量な装具で、靴を履いたままでも使用できる
・足関節背屈アシスト装具:バネやゴムの力で足関節の背屈をサポートする
患者の生活スタイルや症状の程度に合わせて、適切な装具が選択されます。
手術療法
神経に対する手術
圧迫されている神経を周囲の組織から剥離する神経剥離術や、神経が断裂している場合に断端を縫い合わせる神経縫合術が行われることがあります。断裂部分が大きい場合には、他の部位から神経を移植する神経移植術も検討されます。
これらの手術は、神経の回復可能性がある場合に選択されますが、完全な機能回復が得られるとは限らず、術後のリハビリテーションも重要です。
腱移行術
神経の回復が見込めない場合には、他の筋肉の腱を利用して足関節の背屈機能を再建する腱移行術が検討されます。例えば、後脛骨筋腱を前方に移行させて足関節の背屈を可能にする術式などがあります。これにより、神経機能が回復しなくても、代償的に足関節の動きを改善することができます。
その他の手術
重度の下垂足に対しては足関節を機能的な位置で固定する距踵関節固定術が行われることもあります。また、ガングリオンなどの腫瘤による圧迫が原因の場合はその摘出手術が優先されます。
治療選択の目安
治療法の選択については、まず原因の診断が重要です。圧迫性の原因がある場合はその除去を優先し、保存的療法は通常3ヶ月程度試みられます。この期間に回復が見られない場合や症状が進行する場合は手術が検討されます。骨折や脱臼などの外傷、腫瘤による圧迫が明らかな場合は早期の手術が推奨されることが多いです。
腓骨神経麻痺について自宅でできるケア
腓骨神経麻痺の症状改善や日常生活の質を高めるために、医師やリハビリテーション専門家の指導のもとで自宅でも実践できるケア方法があります。
日常的なエクササイズ
自宅で行えるエクササイズには、足首のストレッチや足指の運動などがあります。座った状態で足首を前後に動かす運動を1日数回、各10~15回程度行うことが効果的です。また、タオルを使って足の甲を手前に引くストレッチも有用です。
足の指を意識的に上下に動かす練習や、床に置いたタオルを足の指でつかむ練習も筋力強化に役立ちます。これらのエクササイズは、麻痺した筋肉の活性化や、関節の拘縮予防に効果があります。
筋力トレーニングとしては、軽い抵抗を加えながら足首を上げる運動を行い、徐々に負荷を増やしていくことが重要です。ただし、過度な負荷は避け、痛みが生じる場合はすぐに中止してください。
生活環境の調整
転倒予防のために、家庭内の環境を見直すことも重要です。絨毯やラグなどつま先が引っかかりやすいものは可能な限り避け、家具の配置を見直して通路を広く確保することが推奨されます。また、十分な照明を確保し、夜間の移動時の安全を確保することも大切です。
適切な履物の選択も重要で、スリッパではなく踵まで覆われているタイプの室内履きを使用しましょう。外出時はヒールの低い足にフィットする靴を選ぶことが望ましく、必要に応じてオーダーメイドの靴や靴の中敷きを検討することも有効です。
医師から処方された装具は指示通りに使用し、自宅内でも装具を使用できるよう生活環境を整えることが重要です。
自己マッサージとケア
下腿の筋肉、特に前脛骨筋(すねの外側)を軽くマッサージすることで、血流を改善し筋緊張を和らげることができます。手のひらや指の腹を使って、筋肉の走行に沿って優しくマッサージします。
温かいタオルや蒸しタオルを使って症状のある部位を温めることも効果的です。温めることで血流が改善し、代謝が活発になり、症状が一時的に緩和することがあります。入浴時にもしっかりと温まることで、全身のリラックス効果と相まって症状の緩和が期待できます。
日常生活上の注意点
歩行時は常に足元に注意を払い、つまずきを防止することが大切です。特に階段の上り下りや不整地では一層の注意が必要です。必要に応じて杖などの歩行補助具を使用することも検討してください。
長時間の正座や足組みなど神経を圧迫する姿勢は避けるべきです。デスクワークなどで長時間座る場合は、定期的に姿勢を変えたり、立ち上がったりして血流を促進することが重要です。また、就寝時の姿勢にも注意し、膝を過度に曲げた状態や、腓骨頭部に圧力がかかる姿勢は避けましょう。
症状の変化があれば速やかに医師に相談し、定期的な診察を受けて回復状況を確認することも大切です。自宅でのケアは専門的な治療の補助的な役割を果たすものであり、医師による適切な診断と治療計画が最も重要であることを忘れないでください。
お気軽にご相談ください
当院では、腓骨神経麻痺の患者さまの症状や状態を総合的に評価し、適切なプランを提供します。鍼灸治療を含むさまざまなアプローチを用いて、患者さまの症状の緩和や生活の質の向上に努めます。専門的な知識と経験豊富なスタッフが、患者さまの健康をサポートします。まずはお気軽にご相談ください。
その他の対象疾患
-
眼科系
- VDT症候群
- アレルギー結膜炎
- シェーグレン症候群
- ドライアイ
- バセドウ病眼症
- ぶどう膜炎
- ポスナーシュロスマン症候群
- ホルネル症候群
- レーベル病
- 遠視
- 黄斑ジストロフィ
- 黄斑変性
- 黄班円孔
- 加齢黄斑変性
- 外傷性散瞳
- 外転神経麻痺
- 角膜ヘルペス
- 角膜炎
- 角膜潰瘍
- 角膜内皮障害
- 滑車神経麻痺
- 眼球振盪(眼振)
- 眼球突出症
- 眼筋ミオパチー
- 眼精疲労
- 眼痛
- 眼底出血
- 眼瞼下垂症
- 球後視神経炎
- 逆まつげ
- 強膜炎
- 近視
- 結膜弛緩症
- 原田病
- 交感性眼炎
- 光視症
- 蚕食性角膜潰瘍
- 視神経萎縮
- 視神経炎
- 視神経症
- 斜視
- 弱視
- 硝子体出血
- 硝子体剥離
- 色覚異常
- 増殖性硝子体網膜
- 中心性漿液性網脈絡膜症
- 糖尿病網膜症
- 虹彩毛様体炎
- 白内障
- 飛蚊症
- 複視
- 未熟児網膜症
- 網膜色素変性症
- 網膜静脈閉塞
- 網膜前黄斑線維症
- 網膜剥離
- 乱視
- 緑内障
- 歪視症
-
神経・精神系
- アルツハイマー病
- うつ病
- オリーブ橋小脳萎縮症
- くも膜下出血
- ジスキネジア
- ジストニア
- シャイドレーガー
- しゃっくり
- トロサハント症候群
- ナルコレプシー
- パーキンソン病
- パーキンソン症候群
- バーンアウト症候群
- パニック症候群
- ハンチントン病
- ハント症候群
- フリードライヒ
- ベル麻痺
- マシャド・ジョセフ病
- むずむず脚症候群
- メージュ症候群
- めまい(眩暈)
- モヤモヤ病
- 運動ニューロン病
- 延髄梗塞
- 下垂足
- 過食症
- 過食嘔吐
- 過敏性腸症候群
- 過眠症
- 眼瞼痙攣
- 顔面神経麻痺
- 顔面痛
- 記憶障害
- 起立性調節障害
- 起立性低血圧
- 球脊髄性筋萎縮症
- 拒食症
- 強迫性障害
- 恐怖症
- 胸髄損傷
- 筋ジストロフィー
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- 緊張性頭痛
- 群発頭痛
- 潔癖症
- 幻聴
- 減圧症
- 後頭神経痛
- 腰髄損傷
- 坐骨神経痛
- 三叉神経痛
- 視床出血後遺症
- 歯状核赤核淡蒼球ルイ体萎縮症
- 自律神経失調症
- 失語症
- 社会不安障害
- 重症筋無力症
- 小脳梗塞
- 小脳失調症
- 心身症
- 振戦
- 神経痛
- 神経麻痺
- 進行性核上性麻痺
- 水頭症
- 脊髄空洞症
- 脊髄梗塞
- 脊髄小脳変性症
- 脊髄性筋萎縮症
- 脊髄損傷
- 摂食障害
- 舌咽神経痛
- 線条体黒質変性症
- 前脊髄動脈症候群
- 双極性障害
- 多系統萎縮症
- 多発神経炎
- 多発性硬化症
- 体位性頻脈症候群
- 大脳皮質基底核変性
- 遅発ジスキネジア
- 統合失調症
- 頭痛
- 動眼神経麻痺
- 認知症(痴呆)
- 脳幹梗塞
- 脳幹出血
- 脳梗塞
- 脳梗塞後遺症
- 脳腫瘍
- 脳出血後遺症
- 脳脊髄液減少症
- 脳卒中後遺症
- 脳動脈解離
- 馬尾神経損傷
- 排尿障害
- 排便障害
- 反回神経麻痺
- 不随意運動
- 不眠症
- 片側顔面痙攣
- 片頭痛
- 片麻痺
- 本態性振戦
- 末梢神経障害
- 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
- 慢性疼痛
- 肋間神経痛
- 橈骨神経麻痺
- 痙性斜頸
- 痙攣性発声障害
- 癲癇
- 腓骨神経麻痺
- 頸髄損傷
-
整形外科系
- アキレス腱炎
- アキレス腱滑液包炎
- イップス
- ぎっくり腰
- すべり症
- ばね指
- ペルテス病
- リウマチ
- 乾癬性関節炎
- 関節炎
- 強直性脊椎炎
- 狭窄性腱鞘炎
- 胸郭出口症候群
- 頚椎間板ヘルニア
- 月状骨軟化症
- 肩こり
- 五十肩
- 後縦靭帯骨化症
- 広範腰脊柱管狭窄
- 腰椎間板ヘルニア
- 腰痛
- 骨粗鬆症
- 骨端症(骨端炎)
- 骨軟化症
- 尺骨神経麻痺
- 手根管症候群
- 手足の痛み
- 周期性四肢麻痺
- 書痙
- 寝違え
- 脊柱管狭窄症
- 脊柱側彎症
- 脊椎過敏症
- 脊椎分離症
- 線維筋痛症候群
- 足根管症候群
- 特発性ジストニア
- 背中の痛み
- 膝痛
- 肘部管症候群
- 変形性腰椎症
- 変形性膝関節症
- 変形性頸椎症
- 梨状筋症候群
- 腱鞘炎
- 頸肩腕症候群
- 頸部脊柱管狭窄症