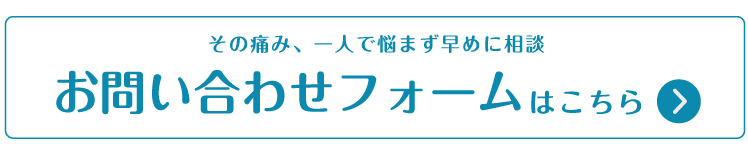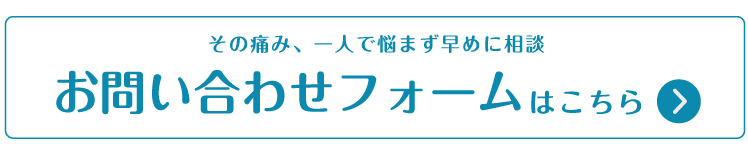眼底出血

眼底出血の症状
眼底出血を起こすと、さまざまな視覚症状が現れることがあります。症状の程度は出血の場所や量によって異なりますが、初期段階では軽微な症状から始まることが多いです。
飛蚊症は眼底出血の代表的な症状の一つです。これは黒い点や線が視界の中をふわふわと漂って見える状態です。生理的に一時的に起こる場合もありますが、眼底出血の場合は持続的に現れることが特徴です。
他にも以下のような症状が見られます。
・視野の一部が霞んで見える(かすみ目)
・視野の中心部が歪んで見える
・視力の低下
・視野が欠ける
特に硝子体出血(眼球内に血液が溜まる状態)を起こした場合には、急激に視力が低下することがあります。症状が進行すると、より深刻な視力障害につながる可能性があるため、早期発見・早期治療が重要です。
眼底出血になると見た目はどうなる?
眼底出血は外から見ただけでは分かりません。これは結膜下出血とは大きく異なる点です。結膜下出血は白目の部分(結膜)の血管が破れて起こるもので、外から見ると明らかな赤い血液が認められます。
一方、眼底出血は網膜の奥にある血管からの出血であるため、外から肉眼で見て分かるものではありません。赤い血液が見えたり、白目が赤くなったりすることはないのです。
眼底出血を確認するためには、眼科での専門的な眼底検査が必要です。検査によって初めて眼底の状態や出血の有無、その程度を確認することができます。
したがって、「見た目で出血がないから眼底出血ではない」とは言えませんので、視覚に何らかの異常を感じた場合は早めに眼科を受診することが大切です。
眼底出血の原因
全身疾患による原因
眼底出血の主な原因として、全身の疾患が関与していることが多くあります。特に以下の疾患が関係しています。
・糖尿病:長期間の高血糖状態により網膜の血管が弱くなり、糖尿病網膜症を引き起こします
・高血圧:血管への負担が増大し、眼底の血管も障害を受けます
・動脈硬化:血管の弾力性が失われ、血管壁がもろくなります
・腎臓病:腎機能の低下により血液の状態が変化し、出血しやすくなります
これらの疾患は血管系に影響を与えるため、眼底の血管にも影響が及び、眼底出血のリスクを高めます。
眼科疾患による原因
全身疾患以外にも、眼そのものの疾患が眼底出血を引き起こすことがあります。
・網膜静脈閉塞症:網膜の静脈が血栓などにより詰まり、血流が滞ることで出血を起こします
・網膜細動脈瘤:網膜の動脈に小さな瘤(こぶ)ができ、その血管壁がもろくなることで出血します
・加齢黄斑変性:年齢とともに黄斑部に異常が生じ、出血を伴うことがあります
・外傷:眼球打撲などの外部からの衝撃により出血することがあります
・後部硝子体剥離:硝子体が網膜から剥がれる際に網膜裂孔を形成し、出血することがあります
これらの病気は早期発見・早期治療が重要であり、定期的な眼科検査が推奨されます。
生活習慣要因
上記の疾患の背景には、生活習慣の乱れが関与していることが多いです。
・不規則な食生活や高脂肪・高塩分食の摂取
・運動不足による代謝の低下
・睡眠不足やストレスの蓄積
・喫煙やアルコールの過剰摂取
特に生活習慣病(高血圧、糖尿病など)の診断を受けている方は、その治療をしっかり行うことで眼底出血の予防にもつながります。
眼底出血でやってはいけないこと
眼底出血を起こした場合、悪化させないために避けるべき行動があります。
まず、激しい運動や重い物の持ち上げなど、血圧を急激に上昇させる行動は避けるべきです。血圧の上昇は出血を悪化させる可能性があります。
また、以下のような行動も控えることが推奨されます。
・目をこする、強く押すなどの刺激を与える行為
・長時間のテレビ視聴やスマートフォン、パソコン操作など目に負担をかける行為
・アルコールの摂取(血管を拡張させる作用がある)
・喫煙(血管を収縮させる作用がある)
さらに、医師の指示なく自己判断で治療を中断したり、薬の服用をやめたりすることも避けるべきです。特に糖尿病や高血圧など基礎疾患がある場合は、その治療を継続することが非常に重要です。
眼底出血を放置すると視力低下や視野欠損など深刻な症状につながる可能性があるため、異変を感じたら早めに専門医に相談することが大切です。
眼底出血の改善方法
西洋医学的治療
眼底出血の改善には、まず原因となる疾患の治療が重要です。特に全身疾患が原因の場合は、その治療が最優先となります。
具体的な治療法としては以下のようなものがあります。
・薬物療法:止血剤や網膜循環改善薬などの内服薬が使用されます
・光凝固術(レーザー治療):レーザーを照射して網膜の障害部位を焼灼し、残った細胞に酸素や栄養が届くよう促します
・抗VEGF硝子体注射:新生血管の形成を抑制する薬剤を直接注射します
・硝子体手術:出血が長期間吸収されない場合、血液で濁った硝子体を切除する手術を行うことがあります
通常、眼底出血は1~3か月程度で自然に吸収・消失することもあります。しかし、出血の程度や場所、原因となる疾患によっては専門的な治療が必要となります。
日常生活での改善
医学的治療と並行して、日常生活での改善も重要です。
・バランスの取れた食事と規則正しい生活習慣の維持
・適度な運動(ただし激しい運動は避ける)
・十分な睡眠とストレス管理
・禁煙とアルコール摂取の制限
・定期的な眼科検診の受診
特に基礎疾患(糖尿病、高血圧など)がある場合は、その管理を徹底することが眼底出血の予防と改善につながります。
眼底出血の鍼灸治療・ツボ
鍼灸治療の特徴
眼底出血に対する鍼灸治療は、血液循環を改善し、出血の吸収を促進する効果が期待されています。また、神経系の調整を通じて目の機能回復を促す可能性もあります。
臨床経験によれば、早期に鍼灸治療を開始すると、眼底出血の回復が早まる可能性があります。ある臨床報告では、鍼灸治療により改善した例は85%に達したとされています。
主要なツボとその効果
眼底出血の鍼灸治療では、以下のようなツボが使用されることが多いです。
・眼底穴:目の奥の血液循環を改善する効果があります
・球後穴:眼球の後ろの血液循環を促進します
・太陽穴:目の疲れを取り、視力回復に効果があるとされています
・晴明穴:目の充血や疲れを改善します
・翳風穴:目の血液循環を改善し、視力回復を促します
・養老穴:目の機能を調整します
・合穀穴:全身の気の流れを整え、血行を促進します
・百会穴:頭部の血流を改善します
・風池穴:頭部と目の血液循環を促進します
これらのツボに対して、微電流を流す方法や、灸頭鍼(鍼の上で艾を燃やす方法)などが用いられることがあります。
治療上の注意点
眼底穴と球後穴は、他のツボより痛みが出やすいため、治療を受ける前に医師や施術者と十分に相談することが重要です。また、鍼灸治療は補完的な治療法として考え、必要に応じて西洋医学的治療と併用することが望ましいでしょう。
鍼灸治療は体質や症状によって効果に個人差があるため、専門家と相談しながら継続的に治療を受けることが大切です。
片目だけ眼底出血になる原因は?
眼底出血は片眼で起こることが多く、両眼同時に発症することは比較的少ないです。そのため、普段は両目で生活している私たちは、視力低下などの症状に気づかないことがあります。
片目だけに眼底出血が起こる主な原因としては、以下のようなものが考えられます。
・局所的な血管の脆弱性:片方の目だけに血管の弱い部分がある場合
・網膜静脈閉塞症:特定の静脈が血栓などで閉塞することで、片側だけに症状が現れる
・網膜細動脈瘤:片側の網膜動脈に瘤が形成された場合
・外傷:片目だけが外部からの衝撃を受けた場合
・部分的な網膜剥離:網膜剥離が片側だけに起きている場合
全身疾患(糖尿病や高血圧など)が原因の場合でも、血管の状態によって片側だけに症状が現れることがあります。しかし、基礎疾患がある場合は、もう片方の目にも同様の症状が現れるリスクが高まるため、定期的な検査が重要です。
注意すべき点として、網膜中心静脈閉塞症による片側の眼底出血があった人は、その後に脳血栓を起こす危険性が高いという報告もあります。したがって、片目の眼底出血を発見した場合も、全身の健康状態に注意を払う必要があります。
片目だけに症状があっても、両目で見ているとなかなか気づきにくいため、定期的な眼科検診を受けることが早期発見につながります。
お気軽にご相談ください
当院では、眼底出血の患者さまの症状や状態を総合的に評価し、最適な治療プランを提供します。鍼灸治療を含むさまざまなアプローチを用いて、患者さまの症状の緩和や生活の質の向上に努めます。専門的な知識と経験豊富なスタッフが、患者さまの健康をサポートします。まずはお気軽にご相談ください。
その他の対象疾患
-
眼科系
- VDT症候群
- アレルギー結膜炎
- シェーグレン症候群
- ドライアイ
- バセドウ病眼症
- ぶどう膜炎
- ポスナーシュロスマン症候群
- ホルネル症候群
- レーベル病
- 遠視
- 黄斑ジストロフィ
- 黄斑変性
- 黄班円孔
- 加齢黄斑変性
- 外傷性散瞳
- 外転神経麻痺
- 角膜ヘルペス
- 角膜炎
- 角膜潰瘍
- 角膜内皮障害
- 滑車神経麻痺
- 眼球振盪(眼振)
- 眼球突出症
- 眼筋ミオパチー
- 眼精疲労
- 眼痛
- 眼底出血
- 眼瞼下垂症
- 球後視神経炎
- 逆まつげ
- 強膜炎
- 近視
- 結膜弛緩症
- 原田病
- 交感性眼炎
- 光視症
- 蚕食性角膜潰瘍
- 視神経萎縮
- 視神経炎
- 視神経症
- 斜視
- 弱視
- 硝子体出血
- 硝子体剥離
- 色覚異常
- 増殖性硝子体網膜
- 中心性漿液性網脈絡膜症
- 糖尿病網膜症
- 虹彩毛様体炎
- 白内障
- 飛蚊症
- 複視
- 未熟児網膜症
- 網膜色素変性症
- 網膜静脈閉塞
- 網膜前黄斑線維症
- 網膜剥離
- 乱視
- 緑内障
- 歪視症
-
神経・精神系
- アルツハイマー病
- うつ病
- オリーブ橋小脳萎縮症
- くも膜下出血
- ジスキネジア
- ジストニア
- シャイドレーガー
- しゃっくり
- トロサハント症候群
- ナルコレプシー
- パーキンソン病
- パーキンソン症候群
- バーンアウト症候群
- パニック症候群
- ハンチントン病
- ハント症候群
- フリードライヒ
- ベル麻痺
- マシャド・ジョセフ病
- むずむず脚症候群
- メージュ症候群
- めまい(眩暈)
- モヤモヤ病
- 運動ニューロン病
- 延髄梗塞
- 下垂足
- 過食症
- 過食嘔吐
- 過敏性腸症候群
- 過眠症
- 眼瞼痙攣
- 顔面神経麻痺
- 顔面痛
- 記憶障害
- 起立性調節障害
- 起立性低血圧
- 球脊髄性筋萎縮症
- 拒食症
- 強迫性障害
- 恐怖症
- 胸髄損傷
- 筋ジストロフィー
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- 緊張性頭痛
- 群発頭痛
- 潔癖症
- 幻聴
- 減圧症
- 後頭神経痛
- 腰髄損傷
- 坐骨神経痛
- 三叉神経痛
- 視床出血後遺症
- 歯状核赤核淡蒼球ルイ体萎縮症
- 自律神経失調症
- 失語症
- 社会不安障害
- 重症筋無力症
- 小脳梗塞
- 小脳失調症
- 心身症
- 振戦
- 神経痛
- 神経麻痺
- 進行性核上性麻痺
- 水頭症
- 脊髄空洞症
- 脊髄梗塞
- 脊髄小脳変性症
- 脊髄性筋萎縮症
- 脊髄損傷
- 摂食障害
- 舌咽神経痛
- 線条体黒質変性症
- 前脊髄動脈症候群
- 双極性障害
- 多系統萎縮症
- 多発神経炎
- 多発性硬化症
- 体位性頻脈症候群
- 大脳皮質基底核変性
- 遅発ジスキネジア
- 統合失調症
- 頭痛
- 動眼神経麻痺
- 認知症(痴呆)
- 脳幹梗塞
- 脳幹出血
- 脳梗塞
- 脳梗塞後遺症
- 脳腫瘍
- 脳出血後遺症
- 脳脊髄液減少症
- 脳卒中後遺症
- 脳動脈解離
- 馬尾神経損傷
- 排尿障害
- 排便障害
- 反回神経麻痺
- 不随意運動
- 不眠症
- 片側顔面痙攣
- 片頭痛
- 片麻痺
- 本態性振戦
- 末梢神経障害
- 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
- 慢性疼痛
- 肋間神経痛
- 橈骨神経麻痺
- 痙性斜頸
- 痙攣性発声障害
- 癲癇
- 腓骨神経麻痺
- 頸髄損傷
-
整形外科系
- アキレス腱炎
- アキレス腱滑液包炎
- イップス
- ぎっくり腰
- すべり症
- ばね指
- ペルテス病
- リウマチ
- 乾癬性関節炎
- 関節炎
- 強直性脊椎炎
- 狭窄性腱鞘炎
- 胸郭出口症候群
- 頚椎間板ヘルニア
- 月状骨軟化症
- 肩こり
- 五十肩
- 後縦靭帯骨化症
- 広範腰脊柱管狭窄
- 腰椎間板ヘルニア
- 腰痛
- 骨粗鬆症
- 骨端症(骨端炎)
- 骨軟化症
- 尺骨神経麻痺
- 手根管症候群
- 手足の痛み
- 周期性四肢麻痺
- 書痙
- 寝違え
- 脊柱管狭窄症
- 脊柱側彎症
- 脊椎過敏症
- 脊椎分離症
- 線維筋痛症候群
- 足根管症候群
- 特発性ジストニア
- 背中の痛み
- 膝痛
- 肘部管症候群
- 変形性腰椎症
- 変形性膝関節症
- 変形性頸椎症
- 梨状筋症候群
- 腱鞘炎
- 頸肩腕症候群
- 頸部脊柱管狭窄症