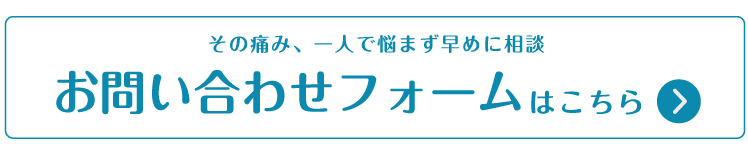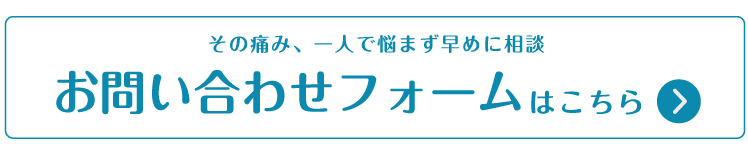耳管開放症

耳管開放症の症状
耳管開放症は、通常は閉じている耳管が開いたままになることで引き起こされる疾患です。この症状は日常生活に大きな影響を与え、不快感をもたらすことがあります。
主な症状
耳管開放症の主な症状は、耳閉感(耳が詰まった感じ)、自声強聴(自分の声が響いて聞こえる)、自己呼吸音聴取(自分の呼吸の音が聞こえる)の3つがあります。これらは「耳管開放症の3主徴」とも呼ばれています。
自声強聴は患者の90%以上に見られる最も一般的な症状です。これは開放している耳管を通って自分の声が咽頭から中耳に直接伝わることで生じます。自分の声が異常に大きく響いて聞こえるため、会話中に自分の声の大きさをコントロールすることが難しくなります。
耳閉感は、耳が詰まったような不快な感覚を指します。ただし、この症状は耳管開放症に特有のものではなく、多くの耳疾患でも現れるため、単独では診断の決め手にはなりません。
自己呼吸音聴取は、自分の呼吸の音が耳に響いて聞こえる症状で、耳管開放症以外ではほとんど見られない特異的な症状です。出現率は3主徴の中で最も低く70%以下ですが、この症状がある場合は耳管開放症を強く疑うことができます。
体位による症状の変化
耳管開放症の特徴的な点として、体位による症状の変化があります。通常、立位や座位で症状が現れますが、横になる(臥位)や深くお辞儀をするように頭を下げる姿勢をとると、症状が一時的に軽快または消失することがあります。これは耳管の近くにある翼突筋静脈叢が体位変化により容量を変化させ、臥位または前屈位になると耳管壁を圧迫して内腔を狭くするためです。
ただし、重度の耳管開放症の場合は、姿勢による症状の軽減が見られないこともあります。
耳鼻科での他覚所見
医療機関では、耳管開放症の診断のために以下のような所見を確認します。
・鼓膜の呼吸性動揺:呼吸に合わせて鼓膜が動く様子が観察されます。これは耳管開放症の最も捉えやすい他覚的所見です。・話声の聴取:医師が患者の耳と自分の耳を聴診チューブでつなぎ、患者の発声音を聴くと、耳管が開いている場合は声が大きく響いて聞こえます。
・耳管機能検査:専門的な検査で耳管の開放状態を確認します。
・座位CT検査:一部の医療機関では座位でのCT検査を行い、耳管の開放状態を画像で確認します。
耳管開放症のセルフチェック
耳管開放症かどうかを自分で確認するためのセルフチェックリストを以下に示します。複数の項目に当てはまる場合は、耳管開放症の可能性があります。
セルフチェックリスト
以下の症状や状況に当てはまるかをチェックしてみましょう。
・□ 立っているときや座っているときに耳が詰まった感じがする・□ 横になると症状が改善する
・□ 頭を深く下げると症状が一時的に良くなる
・□ 自分の声が異常に大きく響いて聞こえる
・□ 自分の呼吸音が聞こえる
・□ エレベーターや高度変化がないのに突然耳の詰まりを感じる
・□ 最近急激な体重減少があった
・□ 長時間立ち仕事をしている
・□ 妊娠中または女性ホルモン薬を使用している
・□ 激しい運動後や汗をかいた後に症状が出る
・□ 鼻をすする癖がある
・□ 水分摂取が少ない
複数の項目に当てはまり、特に横になったり頭を下げたりしたときに症状が改善する場合は、耳管開放症の可能性が高いと言えます。
簡易診断法
自宅で簡単にできる診断方法として、以下のテストがあります。
-
・頭位変換テスト:立っているときに症状があれば、深くお辞儀をしたり横になったりしてみます。症状が改善すれば耳管開放症の可能性があります。
・耳の下圧迫テスト:耳の下(耳たぶの下、顎関節の前方)を指で軽く圧迫します。症状が改善すれば耳管開放症の可能性があります。
・症状出現パターンの確認:朝より夕方に症状が強くなる、運動後に症状が出る、長時間立っていると症状が出るなどのパターンがある場合は耳管開放症を疑います。
これらのセルフチェックで耳管開放症が疑われる場合は、耳鼻科を受診して正確な診断を受けることをお勧めします。特に症状が長期間続く場合や日常生活に支障をきたす場合は、専門医の診察が必要です。
耳管開放症の原因
耳管開放症は様々な要因によって引き起こされる可能性があります。主な原因を以下に詳しく説明します。
体重減少・脱水
耳管開放症の最も一般的な原因の一つは急激な体重減少です。
・過度のダイエット:急激な減量により耳管周囲の脂肪組織が減少すると、耳管を支える構造が弱まり、閉じる機能が低下します。・脱水状態:水分不足により耳管周囲の組織の水分が減少し、むくみが取れることで耳管が開きやすくなります。特に激しい運動後や暑い季節に症状が出ることがあります。
・全身疾患による体重減少:病気により体重が急激に減少した場合も同様のメカニズムで耳管開放症を引き起こすことがあります。
ホルモンバランスの変化
ホルモンの変動も耳管開放症の原因となることがあります。
・妊娠:妊娠中のホルモン変化により耳管開放症を発症することがあり、妊婦の約6人に1人の割合で症状が現れるとされています。・女性ホルモン薬:経口避妊薬などの女性ホルモン薬の使用によっても症状が引き起こされることがあります。
・ホルモン変動期:更年期など、体内のホルモンバランスが大きく変化する時期にも発症リスクが高まります。
自律神経の乱れと血行不良
精神的・身体的ストレスによる自律神経の乱れも重要な要因です。
・交感神経の過剰活動:ストレス状態では交感神経が優位になり、末梢血管の収縮により耳管周囲の血流が低下します。これにより耳管周囲の組織のうっ血が解消され、耳管が開きやすくなります。・長時間の立ち姿勢:長時間立っていると血液が下半身に溜まり、上半身特に頭部の血流が減少します。その結果、耳管周囲の血管のボリュームも減少し、耳管が開放しやすくなります。
・デスクワークなどの姿勢:長時間同じ姿勢でいることで、頸部や肩の筋肉の緊張が生じ、血行不良を引き起こすことがあります。
鼻・咽頭の問題
鼻や咽頭の状態も耳管開放症に影響を与えることがあります。
・上気道炎や副鼻腔炎:風邪などによる上気道の炎症や副鼻腔炎に伴う後鼻漏が耳管開口部周囲に炎症を引き起こし、耳管の機能に影響を与えることがあります。・アレルギー性鼻炎:アレルギー反応による鼻粘膜の腫れが耳管に影響を及ぼすこともあります。
・鼻すすり癖:鼻をすする習慣がある人は、鼻腔内に陰圧が生じ、耳管が開きやすくなることがあります。また、鼻すすりを繰り返すことで耳管の機能が低下することもあります。
先天的・構造的要因
生まれつきの要因や加齢による変化も原因となることがあります。
・耳管の構造的脆弱性:生まれつき耳管の閉鎖機能が弱い場合があります。・加齢による変化:加齢に伴い耳管を支える組織の弾力性が低下することで、耳管開放症のリスクが高まることがあります。
・頸椎の異常:頸椎の変形や異常が耳管周囲の構造に影響を与え、耳管開放症の原因となることもあります。
耳管開放症は、これらの複数の要因が組み合わさって発症することも多く、原因を特定するのが難しい場合もあります。症状の程度や持続時間は原因によって異なることがあります。
耳管開放症のツボ・鍼灸治療
耳管開放症に対する鍼灸治療は、西洋医学的な治療で改善しない場合の選択肢として注目されています。東洋医学の観点から、耳管開放症は「腎」と「肝」の機能低下が関係していると考えられています。
東洋医学的な考え方
東洋医学では、耳の機能は「腎」と深く関連していると考えられています。「腎は耳に開竅する」という考え方があり、聴覚が腎の状態と密接に関わっているとされています。
東洋医学における「腎」は西洋医学の腎臓とは異なり、生長・発育・生殖・水液代謝を司る機能を持っています。腎の精気が十分であれば聴覚機能は正常に働き、不足すると聴覚機能が低下すると考えられています。
また、「肝」には「疏泄をつかさどる」という役割があり、気・血・水の流れを調整し、自律神経系の機能を円滑に保つ働きがあります。「肝」と「腎」は「肝腎同源」と言われるほど深い関係にあり、同時に障害されると耳管開放症を引き起こしやすいと考えられています。
主要なツボと効果
耳管開放症の鍼灸治療で用いられる主なツボには以下のようなものがあります。
・翳風(えいふう):耳の後ろにあるツボで、耳の機能を調整する働きがあります。・聴宮(ちょうきゅう):耳の前にあるツボで、耳の不調に効果があります。
・聴会(ちょうえ):耳の上にあるツボで、耳鳴りや難聴に効果があります。
・耳門(じもん):耳のすぐ前にあるツボで、聴覚機能を調整します。
・足三里(あしさんり):膝の下外側にあるツボで、全身の気を調整し、免疫力を高める効果があります。
・三陰交(さんいんこう):足首の内側にあるツボで、腎の機能を強化し、水液代謝を促進します。
・太渓(たいけい):足首の内側にあるツボで、腎の機能を高める効果があります。
・風池(ふうち):後頭部の付け根にあるツボで、頭部の血流を改善します。
鍼灸治療のプロセス
鍼灸治療では、一般的に以下のようなプロセスで施術が行われます。
1. 自律神経調整
まず仰向けで自律神経調整療法を行い、体のリラックス状態を促進します。特に交感神経の過剰な活動を抑え、副交感神経の活動を高めることで、全身の緊張状態を緩和します。体が冷えている場合は、お灸療法も併用して体を温めます。
2. 首肩の筋緊張緩和
うつ伏せになり、首や肩の筋緊張をほぐす施術を行います。僧帽筋や胸鎖乳突筋などの筋肉の過緊張は耳の血行不良を招くため、これらの筋肉をほぐすことで血行改善を目指します。また、「腎」や「肝」に関連する重要な経穴を刺激し、これらの機能を調整します。
3. 耳周辺の集中施術
横向きになり、症状のある耳側を上にして、耳周辺を集中的に施術します。耳や耳周辺の血流を改善し、耳管の機能調整を図ります。状態に応じて、耳周りに鍼を刺して電気を流す通電療法も行うことがあります。
治療の効果と期間
鍼灸治療の効果は個人差がありますが、多くの場合、数回の治療で症状の改善が見られ始めます。症状が重い場合や長期間続いている場合は、より多くの治療回数が必要になることがあります。
初期の治療では、症状が一時的に軽減した後に再発することもありますが、継続的な治療により次第に効果の持続時間が長くなり、最終的には症状が安定することを目指します。
体質改善のためには、症状が改善した後も定期的なメンテナンス治療が推奨されることがあります。これにより耳管開放症の再発予防だけでなく、全身の健康維持にも役立ちます。
鍼灸治療は西洋医学的な治療と併用することも可能で、総合的なアプローチにより効果を高めることができます。
耳管開放症における漢方
耳管開放症の治療において、漢方薬は重要な役割を果たすことがあります。漢方薬は体質や症状に合わせて処方され、根本的な体質改善を目指すため、耳管開放症の長期的な管理に適しています。
代表的な漢方薬
耳管開放症に用いられる主な漢方薬には以下のようなものがあります。
加味帰脾湯(かみきひとう)
最も一般的に処方される漢方薬の一つです。気血両虚(気と血の両方が不足している状態)に用いられ、特に以下のような症状がある方に適しています。
・疲れやすい・食欲不振
・不眠
・動悸
・不安感
・精神的なストレスが多い
加味帰脾湯は血液循環を改善し、自律神経系のバランスを整える効果があります。耳管周囲の血流を促進し、耳管の機能を正常化する効果が期待されます。
補中益気湯(ほちゅうえっきとう)
気虚(気の不足)に用いられる漢方薬で、以下のような症状がある方に適しています。
・疲労感が強い・食欲不振
・胃腸の働きが弱い
・汗をかきやすい
・免疫力が低下している
補中益気湯は体の中心となる脾・胃の機能を高め、気の生成を促進します。全身の機能を高めることで、耳管開放症の根本的な原因に対応できる可能性があります。
柴胡加竜骨牡蛎湯(さいこかりゅうこつぼれいとう)
自律神経の乱れが原因の場合に用いられる漢方薬です。以下のような症状がある方に適しています。
・精神的な緊張やイライラ・不安感
・不眠
・動悸
・めまい
自律神経のバランスを整え、精神的な安定をもたらす効果があります。ストレスが原因で耳管開放症を発症している場合に有効な場合があります。
四君子湯(しくんしとう)
体力が低下している方に用いられる基本的な漢方薬です。以下のような症状がある方に適しています。
・食欲不振・胃腸の働きが弱い
・倦怠感
・風邪をひきやすい
気を補い、消化機能を高める効果があります。体重減少が原因の耳管開放症に対して、体力を回復させる目的で用いられることがあります。
漢方薬の選び方
漢方薬は西洋医学の薬とは異なり、病名だけでなく患者の体質や症状の特徴に基づいて選択されます。そのため、同じ耳管開放症でも、人によって処方される漢方薬が異なることがあります。
漢方薬の選び方の基本的な考え方は以下の通りです。
-
・証(しょう)の判断:東洋医学では、症状の現れ方や体質を総合的に評価して「証」を判断します。証に基づいて最適な漢方薬が選ばれます。
・気・血・水のバランス:気(エネルギー)、血(血液)、水(体液)のバランスを整えることを目的として漢方薬が選ばれます。耳管開放症の場合、特に気虚(気の不足)や血虚(血の不足)が関係していることが多いです。
・体質の考慮:虚証(体力が低下している状態)か実証(体力があり症状も強い状態)かを判断し、適切な漢方薬を選びます。耳管開放症では、多くの場合虚証に対する漢方薬が選ばれます。
漢方薬の効果と服用の注意点
漢方薬は即効性は低いものの、長期的に服用することで体質改善が期待できます。一般的に以下のような効果が期待されます。
・自律神経のバランス調整・血液循環の改善
・体力・免疫力の向上
・ストレス耐性の向上
漢方薬を服用する際の注意点
・効果が現れるまでに通常2〜4週間程度かかることがあります・指示された用法・用量を守りましょう
・他の薬と併用する場合は医師や薬剤師に相談しましょう
・体質や症状に合っていない場合は効果が出ないことがあります
・症状の変化があれば医師に相談しましょう
漢方薬は副作用が少ないとされていますが、人によっては胃腸障害や発疹などが現れることもあります。異常を感じた場合は医師に相談してください。
耳管開放症でやってはいけないこと
耳管開放症の症状を悪化させたり、合併症を引き起こしたりする可能性のある行動や習慣があります。以下に、耳管開放症の方が避けるべきことを詳しく説明します。
鼻すすりの習慣
耳管開放症の症状がある方が最も注意すべきことの一つが「鼻すすり」です。
鼻すすりとは、鼻水を吸い込むように鼻から空気を強く吸引する行為です。多くの人が無意識にこの行為を行っていますが、耳管開放症の症状を一時的に緩和するために習慣的に鼻すすりをすることは非常に危険です。
鼻すすりをすると以下のような問題が生じる可能性があります。
・中耳への陰圧の発生:鼻をすすることで鼻腔内に強い陰圧が生じ、これが耳管を通じて中耳に伝わります。・中耳炎のリスク増加:繰り返し陰圧がかかることで、滲出性中耳炎を引き起こす可能性があります。
・癒着性中耳炎の発症:長期間にわたって鼻すすりを続けると、鼓膜が内側に引き込まれ、中耳腔の壁と癒着する癒着性中耳炎を引き起こすことがあります。
・真珠腫性中耳炎の発症:最も深刻な合併症として、真珠腫性中耳炎を発症するリスクがあります。これは中耳に皮膚組織が侵入して増殖する病態で、難聴や顔面神経麻痺などを引き起こす可能性があります。
症状がある時は、鼻すすりではなく、横になる、頭を下げる、あるいは医師に相談して適切な対処法を学ぶことが重要です。
過度のダイエット
急激な体重減少は耳管開放症の主要な原因の一つです。健康的な体重を維持することが重要で、以下のような無理なダイエットは避けるべきです。
・極端な食事制限:必要な栄養素を摂取できなくなるだけでなく、急激な体重減少により耳管周囲の脂肪組織も減少し、耳管が開放しやすくなります。・過度の運動:激しい運動による急速な体重減少や脱水状態も症状を悪化させる可能性があります。
・プチ断食などの極端な方法:短期間で大幅に体重を減らす方法は、体に大きな負担をかけ、耳管開放症の症状を悪化させる可能性があります。
体重管理が必要な場合は、栄養バランスのとれた食事と適度な運動で緩やかに体重を減らす方法を選びましょう。
水分摂取不足
脱水状態は耳管開放症の症状を悪化させる要因となります。
・水分摂取量の不足:体内の水分が不足すると、耳管周囲の組織も水分が減少し、耳管が開放しやすくなります。・夏場や運動時の注意:特に暑い季節や運動後は積極的に水分を補給する必要があります。
・アルコールやカフェインの過剰摂取:これらは利尿作用があり、体内の水分を失わせるため、過剰な摂取は避けるべきです。
一日あたり1.5〜2リットル程度の水分摂取を心がけ、特に症状が出やすい状況では意識的に水分を補給することが重要です。
長時間の立ち姿勢
長時間立ち続けることは、耳管開放症の症状を悪化させる可能性があります。
・血液の下肢への貯留:長時間立っていると血液が下肢に溜まり、頭部や耳管周囲の血流が減少します。・耳管周囲組織の血流低下:血流が減少すると、耳管周囲の組織のボリュームが減り、耳管が開放しやすくなります。
・疲労やストレスの蓄積:長時間の立ち仕事は全身の疲労やストレスを蓄積させ、自律神経のバランスを崩す原因となります。
立ち仕事の方は、定期的に座って休憩をとる、足を高くして休むなどの工夫をしましょう。また、適度に姿勢を変えることも重要です。
その他避けるべきこと
・カフェイン過剰摂取:コーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンクなどに含まれるカフェインは、自律神経に影響を与え、症状を悪化させる可能性があります。・ストレスの蓄積:精神的ストレスは自律神経のバランスを崩し、症状を悪化させることがあります。ストレス管理の方法を身につけることが重要です。
・不規則な生活習慣:睡眠不足や不規則な食事など生活リズムの乱れは、体調を崩しやすくし、症状の悪化につながることがあります。
・自己判断での治療中断:症状が一時的に改善したからといって、医師の指示なく治療を中断することは避けるべきです。
耳管開放症の管理には、これらの避けるべき行動を理解し、生活習慣の改善と医師の指示に従った適切な治療が重要です。症状が気になる場合は、自己判断せずに医療機関を受診しましょう。
耳管開放症を放置するとどうなる?
耳管開放症を放置すると、様々な影響が生じる可能性があります。症状の進行や合併症の発症リスク、そして日常生活への影響について詳しく説明します。
症状の進行
耳管開放症を放置すると、症状が進行したり悪化したりする可能性があります。
・症状の慢性化:初期段階では一時的だった症状が、放置することで常時出現するようになることがあります。・症状の重症化:軽度の耳閉感や自声強聴が、より顕著になり、生活に大きな支障をきたすレベルまで悪化することがあります。
・自然治癒の困難化:初期の段階では生活習慣の改善などで自然に回復することもありますが、長期間放置すると治療にも反応しにくくなる可能性があります。
お気軽にご相談ください
当院では、耳管開放症の患者さまの症状や状態を総合的に評価し、適切なプランを提供します。鍼灸治療を含むさまざまなアプローチを用いて、患者さまの症状の緩和や生活の質の向上に努めます。専門的な知識と経験豊富なスタッフが、患者さまの健康をサポートします。まずはお気軽にご相談ください。
その他の対象疾患
-
眼科系
- VDT症候群
- アレルギー結膜炎
- シェーグレン症候群
- ドライアイ
- バセドウ病眼症
- ぶどう膜炎
- ポスナーシュロスマン症候群
- ホルネル症候群
- レーベル病
- 遠視
- 黄斑ジストロフィ
- 黄斑変性
- 黄班円孔
- 加齢黄斑変性
- 外傷性散瞳
- 外転神経麻痺
- 角膜ヘルペス
- 角膜炎
- 角膜潰瘍
- 角膜内皮障害
- 滑車神経麻痺
- 眼球振盪(眼振)
- 眼球突出症
- 眼筋ミオパチー
- 眼精疲労
- 眼痛
- 眼底出血
- 眼瞼下垂症
- 球後視神経炎
- 逆まつげ
- 強膜炎
- 近視
- 結膜弛緩症
- 原田病
- 交感性眼炎
- 光視症
- 蚕食性角膜潰瘍
- 視神経萎縮
- 視神経炎
- 視神経症
- 斜視
- 弱視
- 硝子体出血
- 硝子体剥離
- 色覚異常
- 増殖性硝子体網膜
- 中心性漿液性網脈絡膜症
- 糖尿病網膜症
- 虹彩毛様体炎
- 白内障
- 飛蚊症
- 複視
- 未熟児網膜症
- 網膜色素変性症
- 網膜静脈閉塞
- 網膜前黄斑線維症
- 網膜剥離
- 乱視
- 緑内障
- 歪視症
-
神経・精神系
- アルツハイマー病
- うつ病
- オリーブ橋小脳萎縮症
- くも膜下出血
- ジスキネジア
- ジストニア
- シャイドレーガー
- しゃっくり
- トロサハント症候群
- ナルコレプシー
- パーキンソン病
- パーキンソン症候群
- バーンアウト症候群
- パニック症候群
- ハンチントン病
- ハント症候群
- フリードライヒ
- ベル麻痺
- マシャド・ジョセフ病
- むずむず脚症候群
- メージュ症候群
- めまい(眩暈)
- モヤモヤ病
- 運動ニューロン病
- 延髄梗塞
- 下垂足
- 過食症
- 過食嘔吐
- 過敏性腸症候群
- 過眠症
- 眼瞼痙攣
- 顔面神経麻痺
- 顔面痛
- 記憶障害
- 起立性調節障害
- 起立性低血圧
- 球脊髄性筋萎縮症
- 拒食症
- 強迫性障害
- 恐怖症
- 胸髄損傷
- 筋ジストロフィー
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- 緊張性頭痛
- 群発頭痛
- 潔癖症
- 幻聴
- 減圧症
- 後頭神経痛
- 腰髄損傷
- 坐骨神経痛
- 三叉神経痛
- 視床出血後遺症
- 歯状核赤核淡蒼球ルイ体萎縮症
- 自律神経失調症
- 失語症
- 社会不安障害
- 重症筋無力症
- 小脳梗塞
- 小脳失調症
- 心身症
- 振戦
- 神経痛
- 神経麻痺
- 進行性核上性麻痺
- 水頭症
- 脊髄空洞症
- 脊髄梗塞
- 脊髄小脳変性症
- 脊髄性筋萎縮症
- 脊髄損傷
- 摂食障害
- 舌咽神経痛
- 線条体黒質変性症
- 前脊髄動脈症候群
- 双極性障害
- 多系統萎縮症
- 多発神経炎
- 多発性硬化症
- 体位性頻脈症候群
- 大脳皮質基底核変性
- 遅発ジスキネジア
- 統合失調症
- 頭痛
- 動眼神経麻痺
- 認知症(痴呆)
- 脳幹梗塞
- 脳幹出血
- 脳梗塞
- 脳梗塞後遺症
- 脳腫瘍
- 脳出血後遺症
- 脳脊髄液減少症
- 脳卒中後遺症
- 脳動脈解離
- 馬尾神経損傷
- 排尿障害
- 排便障害
- 反回神経麻痺
- 不随意運動
- 不眠症
- 片側顔面痙攣
- 片頭痛
- 片麻痺
- 本態性振戦
- 末梢神経障害
- 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
- 慢性疼痛
- 肋間神経痛
- 橈骨神経麻痺
- 痙性斜頸
- 痙攣性発声障害
- 癲癇
- 腓骨神経麻痺
- 頸髄損傷
-
整形外科系
- アキレス腱炎
- アキレス腱滑液包炎
- イップス
- ぎっくり腰
- すべり症
- ばね指
- ペルテス病
- リウマチ
- 乾癬性関節炎
- 関節炎
- 強直性脊椎炎
- 狭窄性腱鞘炎
- 胸郭出口症候群
- 頚椎間板ヘルニア
- 月状骨軟化症
- 肩こり
- 五十肩
- 後縦靭帯骨化症
- 広範腰脊柱管狭窄
- 腰椎間板ヘルニア
- 腰痛
- 骨粗鬆症
- 骨端症(骨端炎)
- 骨軟化症
- 尺骨神経麻痺
- 手根管症候群
- 手足の痛み
- 周期性四肢麻痺
- 書痙
- 寝違え
- 脊柱管狭窄症
- 脊柱側彎症
- 脊椎過敏症
- 脊椎分離症
- 線維筋痛症候群
- 足根管症候群
- 特発性ジストニア
- 背中の痛み
- 膝痛
- 肘部管症候群
- 変形性腰椎症
- 変形性膝関節症
- 変形性頸椎症
- 梨状筋症候群
- 腱鞘炎
- 頸肩腕症候群
- 頸部脊柱管狭窄症