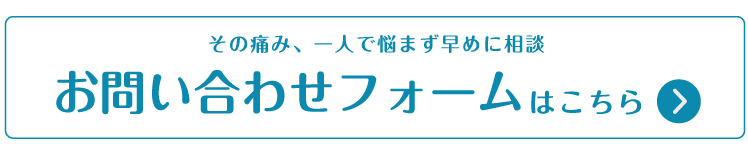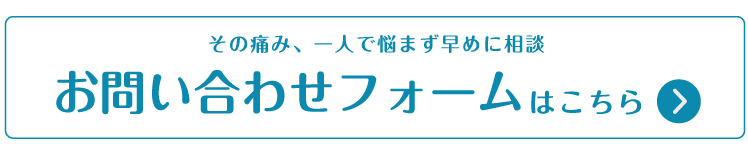顎関節症

顎関節症の症状
顎関節症は、あごを動かす咀嚼筋や、あごの関節を構成する骨や筋肉に異常が起こる疾患です。主な症状として「口が開きにくい(開口障害)」「あごが痛い(開口時痛)」「口を開けると音がする(関節雑音)」などが現れます。
日本人の約半数が生涯で一度は顎関節に何らかの症状を経験するといわれており、特に20〜40代の若い女性と中年女性に多く見られます。多くの場合、片側のみに症状が出ることが特徴的です。
関節雑音については、「カクカク」「ポキポキ」といった音がすることがありますが、関節雑音のみの場合は治療の必要がないとされています。しかし、痛みや開口障害を伴う場合は、早めに治療を開始することが重要です。
患者さんによって症状の現れ方は様々ですが、以下のような症状が単独または複合的に現れることがあります。
・あごを動かすと痛みがある(特に口を大きく開けようとしたとき)
・口を開けるとあごの関節から音がする
・口が十分に開かない
・噛むときに痛みがある
・あごの関節周辺や頬、こめかみに痛みがある
・耳の痛みとして感じることもある
症状が長期間続くと、頭痛や肩こり、腰痛などの全身症状につながることもあります。また、耳鳴りやめまい、目の疲れなど、一見関連がないように思える症状も引き起こすことがあるため、注意が必要です。
顎関節症の原因
顎関節症の原因は一つではなく、多くの要因が複合的に関わる「多因子病因説」が現在の主流な考え方です。様々な要因が重なり、個人の耐久力を超えたときに症状が現れます。タイプ別に主な原因を見ていきましょう。
Ⅰ型(筋肉の障害)
Ⅰ型は主にあごの筋肉(咬筋・側頭筋など)の使いすぎによる筋肉痛のような症状が特徴です。以下のような原因が考えられます。
・ストレスによる無意識の歯ぎしりや食いしばり
・長時間の緊張状態による筋肉の疲労
・TCH(歯列接触癖):上下の歯を無意識に接触させる癖
・スマートフォンの長時間使用による姿勢の悪化
咬筋は頬、側頭筋はこめかみに位置するため、頬やこめかみの痛みとして現れることが多いです。頭痛と勘違いされることもあります。
Ⅱ型(関節靭帯の障害)
Ⅱ型は関節靭帯の異常で、いわば「あごのねんざ」のような状態です。以下のような原因が考えられます。
・無理に口を大きく開けたとき(あくびや大きなものを食べるときなど)
・固いものを食べたとき
・外傷(事故やスポーツなどであごを強打したとき)
・日常的な歯ぎしりや食いしばり
顎関節は耳の穴の直前にあるため、耳の痛みと誤解されることもあります。
Ⅲ型(関節円板の障害)
Ⅲ型は関節円板の異常です。関節円板とは、上あごの骨と下あごの骨の間に存在するクッションのような組織で、通常は頭蓋骨と下顎骨が直接こすれ合わないようにしています。
・関節円板が前方にずれることで「カクカク」「ポキポキ」という関節雑音が発生
・さらにずれが大きくなると開口障害を引き起こす
・長期的な顎関節への負担が原因となることが多い
症状が「関節雑音」だけの場合は特に治療の必要はありませんが、痛みや開口障害を伴う場合は治療が必要です。
Ⅳ型(骨の変形)
Ⅳ型は関節を構成する下顎骨の関節突起の変形によるものです。
・長年の顎関節症が続いた結果として起こることが多い
・加齢による骨の変形
・慢性的な炎症による骨の変化
このタイプは症状だけでは診断が難しく、レントゲンやCTなどの画像検査が必要です。変形した骨を元通りにすることは困難なため、痛みの軽減と十分な開口を目標に治療を行います。
その他の要因
上記の具体的なタイプに加えて、以下のような日常的な要因も顎関節症のリスクを高めます。
・上顎と下顎の大きさのバランスが悪い(出っ歯や受け口など)
・生活習慣(頬杖をつく、片方の歯で噛む、猫背など)
・特定のスポーツや動作(テニスやサッカーなどの食いしばりを伴うスポーツ)
・楽器演奏(特に吹奏楽器)
・精神的ストレス(無意識のうちにあごに力が入りやすくなる)
これらの要因が複合的に関わり合って顎関節症を引き起こすと考えられています。
顎関節症でやってはいけないこと
顎関節症の症状がある場合、以下のような行動は避けるべきです。これらの行動はあごへの負担を増大させ、症状を悪化させる可能性があります。
まず、あごに大きな負担をかける行動は控えましょう。特に以下の行動は注意が必要です。
・大きく口を開ける動作(大あくびなど)
・固いものを噛む(硬い食べ物、ガムなど)
・長時間の会話や歌唱
・頬杖をつく習慣
また、日常生活の中での悪い習慣も顎関節症を悪化させる要因となります。
・歯ぎしりや食いしばり
・爪を噛む、筆記具を噛むなどの癖
・片側だけで噛む習慣
・うつぶせ寝(あごに負担がかかる)
特に重要なのは、TCH(歯列接触癖)に注意することです。これは上下の歯を無意識に接触させる癖で、多くの顎関節症患者に見られます。本来、リラックスしているときは上下の歯は離れているのが正常です。このTCHを意識して減らすだけで症状が改善するケースが非常に多いことから、TCHは顎関節症の最大の要因と考えられています。
さらに、精神的ストレスもあごの筋肉の緊張を高める原因となります。過度のストレスを抱え込まず、適切なストレス発散法を見つけることも大切です。
手術が必要と感じても、関節雑音だけを理由に手術を選択することは世界的には推奨されていません。関節雑音のみの症状であれば、特別な治療は必要ないとされています。
顎関節症になったときにすぐできる対処法
顎関節症の症状が現れた場合、以下のような対処法がすぐに実践できます。これらの方法は症状の緩和に役立ちます。
あごの安静
あごの安静を保つことは最も基本的で重要な対処法です。
・大きな口の開閉を控える
・小さく切った食べ物を選ぶ
・話しすぎない、歌いすぎない
・あくびをするときは手で支える
あごをできるだけ動かさないようにすることで、炎症や痛みを和らげることができます。特に急性期の痛みがある場合は、あごの安静が最優先です。
温めと冷やし
症状の種類や状況に応じて、温めたり冷やしたりする方法も効果的です。
・急性の痛みがある場合:冷たいタオルやアイスパックであごを冷やす(10〜15分程度)
・慢性的な痛みや筋肉の緊張がある場合:蒸しタオルや温湿布であごを温める
温めることで血行が促進され、筋肉の緊張がほぐれます。冷やすことで炎症や腫れを抑える効果があります。
意識的な習慣改善
日常生活での意識改革も即効性のある対処法です。
・TCH(歯列接触癖)に気づいたら意識的に上下の歯を離す
・頬杖をつかない
・片側だけで噛まない
・姿勢を正す
特にTCHへの意識は重要です。上下の歯が接触していることに気づいたら、すぐに歯を離して「上下の歯が離れている状態」を意識しましょう。
リラクゼーション
精神的なストレスがあごの筋肉の緊張を高めることも多いため、リラクゼーション法も効果的です。
・深呼吸(ゆっくりと腹式呼吸を5分程度)
・あごの筋肉のストレッチ(ゆっくりと少しずつ口を開ける運動)
・全身のリラクゼーション(肩や首の力を抜く)
これらの即時対応で症状が改善しない場合や、痛みが強い場合は早めに専門医(歯科医や口腔外科医)に相談しましょう。適切な診断と治療が症状の長期化を防ぐ鍵となります。
顎関節症の鍼灸治療
鍼灸治療は顎関節症に対して効果的なアプローチとして知られています。特に初期の顎関節症であれば、鍼治療で簡単に改善することが多いとされています。
鍼灸治療のメカニズム
鍼灸治療が顎関節症に効果を発揮するメカニズムは以下の通りです。
・筋肉の緊張緩和:あごの周りの緊張した筋肉(咬筋、側頭筋、内外側翼突筋など)を鍼で刺激することで、筋肉の緊張を和らげます。
・血流改善:鍼による刺激は局所の血流を促進し、炎症や痛みの軽減に役立ちます。
・自律神経の調整:鍼灸治療は交感神経の過剰な活動を抑え、副交感神経の働きを促進することで、全身のリラックス効果をもたらします。
・疼痛緩和:鍼刺激によって体内の鎮痛物質(エンドルフィンなど)の分泌が促され、痛みを和らげる効果があります。
鍼灸治療のアプローチ
顎関節症に対する鍼灸治療は、通常、以下のようなステップで行われます。
1. 自律神経の調整:まず全身の自律神経のバランスを整えることから始めます。多くの顎関節症患者は交感神経が過剰に活性化している状態にあります。
2. 頸肩部の緊張緩和:顎関節周辺だけでなく、首や肩の緊張も関連することが多いため、これらの部位の筋緊張も緩和します。
3. 顎関節周辺の直接的な治療:あごの周りの筋肉(咬筋、側頭筋、内外側翼突筋、胸鎖乳突筋など)に直接アプローチします。
鍼灸治療では、症状の程度や原因によって治療方針が異なります。低音の耳鳴りと同様に、筋肉の緊張が主な原因である顎関節症(Ⅰ型)は比較的改善しやすい傾向がありますが、関節円板の異常(Ⅲ型)や骨の変形(Ⅳ型)では、症状の緩和が主な目標となります。
併用療法
鍼灸治療だけでなく、以下のような治療法を組み合わせることでより効果的な結果が期待できます。
・SSP療法(低周波電気刺激療法):患部の血流を改善します。
・超音波療法:深部の組織に働きかけ、循環を促進します。
・手技マッサージ:筋肉や軟部組織の緊張を緩めます。
治療の目安としては、週に1回の頻度で通院し、およそ3ヶ月ほどの治療期間が一般的です。症状が発症してからの期間が短いほど、治療期間も短縮できる傾向があります。
顎関節症に即効性があるツボは?
顎関節症の症状緩和に効果的なツボがいくつかあります。これらのツボは自分でも刺激することができ、症状の軽減に役立つことがあります。
特に顎関節症に効果的な主なツボは以下の通りです。
・下関(げかん):耳の穴の前にあるへこみ、口を開けたときに盛り上がる部分にあります。顎関節症の痛みや開口障害に効果があり、特に口の開閉に違和感があるときに有効です。
・天容(てんよう):下顎角(エラ)のうしろ、胸鎖乳突筋の前方のへこみの部分に位置します。ストレスや精神的緊張によって固くなる場合があるため、ここを緩めることで顎関節症の症状緩和が期待できます。
・頬車(きょうしゃ):咬筋にアプローチできるツボで、下顎角から少し頬に入ったところにあります。力を入れて噛みしめると筋肉が盛り上がり、口を開けると凹むのが特徴です。
・扶突(ふとつ):胸鎖乳突筋に有効とされているツボで、のど仏の指3本分外側の場所に位置します。肩こりや頭痛の症状の緩和にも効果が期待できます。
これらのツボを刺激する方法としては、以下のようなやり方があります。
1. 指の腹を使って、やさしく円を描くように押す 2. 軽く押したままゆっくりと5秒ほど保持し、徐々に力を緩める 3. これを1ヶ所につき3〜5回繰り返す
ツボ刺激は痛みを感じるほど強く押す必要はなく、心地よい刺激を与える程度で効果があります。ただし、症状が強い場合や長期間続く場合は、自己流のツボ刺激だけに頼らず、専門家による適切な治療を受けることをおすすめします。
顎関節症は早期に適切な対処をすることで、多くの場合、症状の改善が期待できます。日常生活での習慣改善と必要に応じた専門治療を組み合わせることで、快適な生活を取り戻しましょう。
お気軽にご相談ください
当院では、顎関節症の患者さまの症状や状態を総合的に評価し、最適な治療プランを提供します。鍼灸治療を含むさまざまなアプローチを用いて、患者さまの症状の緩和や生活の質の向上に努めます。専門的な知識と経験豊富なスタッフが、患者さまの健康をサポートします。まずはお気軽にご相談ください。
その他の対象疾患
-
眼科系
- VDT症候群
- アレルギー結膜炎
- シェーグレン症候群
- ドライアイ
- バセドウ病眼症
- ぶどう膜炎
- ポスナーシュロスマン症候群
- ホルネル症候群
- レーベル病
- 遠視
- 黄斑ジストロフィ
- 黄斑変性
- 黄班円孔
- 加齢黄斑変性
- 外傷性散瞳
- 外転神経麻痺
- 角膜ヘルペス
- 角膜炎
- 角膜潰瘍
- 角膜内皮障害
- 滑車神経麻痺
- 眼球振盪(眼振)
- 眼球突出症
- 眼筋ミオパチー
- 眼精疲労
- 眼痛
- 眼底出血
- 眼瞼下垂症
- 球後視神経炎
- 逆まつげ
- 強膜炎
- 近視
- 結膜弛緩症
- 原田病
- 交感性眼炎
- 光視症
- 蚕食性角膜潰瘍
- 視神経萎縮
- 視神経炎
- 視神経症
- 斜視
- 弱視
- 硝子体出血
- 硝子体剥離
- 色覚異常
- 増殖性硝子体網膜
- 中心性漿液性網脈絡膜症
- 糖尿病網膜症
- 虹彩毛様体炎
- 白内障
- 飛蚊症
- 複視
- 未熟児網膜症
- 網膜色素変性症
- 網膜静脈閉塞
- 網膜前黄斑線維症
- 網膜剥離
- 乱視
- 緑内障
- 歪視症
-
神経・精神系
- アルツハイマー病
- うつ病
- オリーブ橋小脳萎縮症
- くも膜下出血
- ジスキネジア
- ジストニア
- シャイドレーガー
- しゃっくり
- トロサハント症候群
- ナルコレプシー
- パーキンソン病
- パーキンソン症候群
- バーンアウト症候群
- パニック症候群
- ハンチントン病
- ハント症候群
- フリードライヒ
- ベル麻痺
- マシャド・ジョセフ病
- むずむず脚症候群
- メージュ症候群
- めまい(眩暈)
- モヤモヤ病
- 運動ニューロン病
- 延髄梗塞
- 下垂足
- 過食症
- 過食嘔吐
- 過敏性腸症候群
- 過眠症
- 眼瞼痙攣
- 顔面神経麻痺
- 顔面痛
- 記憶障害
- 起立性調節障害
- 起立性低血圧
- 球脊髄性筋萎縮症
- 拒食症
- 強迫性障害
- 恐怖症
- 胸髄損傷
- 筋ジストロフィー
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- 緊張性頭痛
- 群発頭痛
- 潔癖症
- 幻聴
- 減圧症
- 後頭神経痛
- 腰髄損傷
- 坐骨神経痛
- 三叉神経痛
- 視床出血後遺症
- 歯状核赤核淡蒼球ルイ体萎縮症
- 自律神経失調症
- 失語症
- 社会不安障害
- 重症筋無力症
- 小脳梗塞
- 小脳失調症
- 心身症
- 振戦
- 神経痛
- 神経麻痺
- 進行性核上性麻痺
- 水頭症
- 脊髄空洞症
- 脊髄梗塞
- 脊髄小脳変性症
- 脊髄性筋萎縮症
- 脊髄損傷
- 摂食障害
- 舌咽神経痛
- 線条体黒質変性症
- 前脊髄動脈症候群
- 双極性障害
- 多系統萎縮症
- 多発神経炎
- 多発性硬化症
- 体位性頻脈症候群
- 大脳皮質基底核変性
- 遅発ジスキネジア
- 統合失調症
- 頭痛
- 動眼神経麻痺
- 認知症(痴呆)
- 脳幹梗塞
- 脳幹出血
- 脳梗塞
- 脳梗塞後遺症
- 脳腫瘍
- 脳出血後遺症
- 脳脊髄液減少症
- 脳卒中後遺症
- 脳動脈解離
- 馬尾神経損傷
- 排尿障害
- 排便障害
- 反回神経麻痺
- 不随意運動
- 不眠症
- 片側顔面痙攣
- 片頭痛
- 片麻痺
- 本態性振戦
- 末梢神経障害
- 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
- 慢性疼痛
- 肋間神経痛
- 橈骨神経麻痺
- 痙性斜頸
- 痙攣性発声障害
- 癲癇
- 腓骨神経麻痺
- 頸髄損傷
-
整形外科系
- アキレス腱炎
- アキレス腱滑液包炎
- イップス
- ぎっくり腰
- すべり症
- ばね指
- ペルテス病
- リウマチ
- 乾癬性関節炎
- 関節炎
- 強直性脊椎炎
- 狭窄性腱鞘炎
- 胸郭出口症候群
- 頚椎間板ヘルニア
- 月状骨軟化症
- 肩こり
- 五十肩
- 後縦靭帯骨化症
- 広範腰脊柱管狭窄
- 腰椎間板ヘルニア
- 腰痛
- 骨粗鬆症
- 骨端症(骨端炎)
- 骨軟化症
- 尺骨神経麻痺
- 手根管症候群
- 手足の痛み
- 周期性四肢麻痺
- 書痙
- 寝違え
- 脊柱管狭窄症
- 脊柱側彎症
- 脊椎過敏症
- 脊椎分離症
- 線維筋痛症候群
- 足根管症候群
- 特発性ジストニア
- 背中の痛み
- 膝痛
- 肘部管症候群
- 変形性腰椎症
- 変形性膝関節症
- 変形性頸椎症
- 梨状筋症候群
- 腱鞘炎
- 頸肩腕症候群
- 頸部脊柱管狭窄症