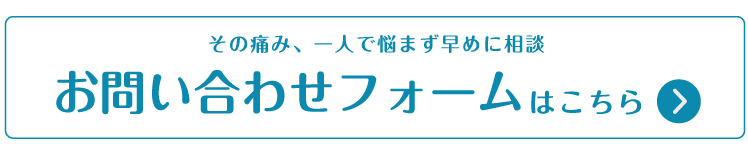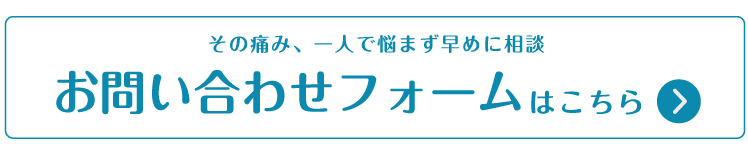耳鳴り

耳鳴りの症状
耳鳴りとは、実際には外部からの音がないにもかかわらず、耳の中や頭の中でさまざまな音が聞こえる現象のことです。およそ1年以内に約640万人の方が耳鳴りを経験するといわれています。
耳鳴りの音の種類は人によって異なり、「キーン」「ジーン」という高い金属音のような音から、「ザー」「ゴー」というような低い音まで様々です。また、その程度も周囲が静かになった時にかすかに感じる程度のものから、日常生活に支障をきたすほど強い症状まで個人差があります。
耳鳴りの症状が長期間続くと、以下のような二次的な症状を引き起こすこともあります。
・睡眠障害(耳鳴りが気になって眠れない)
・集中力の低下
・精神的ストレスの増加
・不安感や抑うつ状態
特に夜間は周囲が静かになるため耳鳴りが気になりやすく、睡眠の質が低下することで日中の生活にも影響を及ぼすことがあります。耳鳴りの多くは鼓膜の周辺ではなく、さらに奥の内耳や聴神経、脳で起きているケースがほとんどであり、難聴を伴うことも少なくありません。
難聴、耳鳴り (hearing loss, tinnitus)|KOMPAS
耳鳴りの原因
耳鳴りは様々な原因で発生します。その原因によって特徴的な症状が現れることもあるため、耳鳴りのタイプ別に主な原因を見ていきましょう。
高音の耳鳴り(「キーン」「ピー」など)
「キーン」「ピー」といった金属音や電子音のような高い音の耳鳴りには、以下のような原因が考えられます。
・突発性難聴:ある日突然、片方の耳が聞こえなくなり、耳鳴りやめまいを伴います。ストレスが関係して発症すると考えられています。発症後1~2週間以内に治療を開始することが重要です。
・メニエール病:突然、ぐるぐる回るような回転性のめまいが起こり、吐き気や嘔吐を伴う病気です。めまいの前後には左右どちらかの耳に耳鳴りや難聴、耳の詰まり感も現れます。内耳のリンパ液が過剰になることが原因と考えられています。
・聴神経腫瘍:神経を包む細胞にできる良性の脳腫瘍です。発症初期から片方の耳に難聴や耳鳴り、ふわふわとした浮遊性のめまいが現れます。
・老人性難聴:加齢により内耳の有毛細胞が老化し、壊れてしまうことで両耳の聞こえが低下する状態です。両耳の耳鳴りを伴うことがあります。
・音響外傷:大音量の音(コンサートやヘッドホン・イヤホンの長時間使用など)により内耳の有毛細胞が傷つくことで発症します。両耳の耳鳴りや耳の痛みを伴うことがあります。
・薬剤性難聴:アスピリンなど特定の薬の副作用で耳の聞こえが低下し、耳鳴りやめまいを伴うことがあります。服用開始後早い時期に両耳に症状が出るのが特徴です。
・ストレスや疲労による自律神経の乱れ:睡眠不足や精神的ストレスにより自律神経のバランスが崩れ、一時的な耳鳴りが発生することがあります。
低音の耳鳴り(「ブーン」「ゴー」「ザー」など)
「ブーン」「ゴー」「ザー」といった重低音の耳鳴りには、以下のような原因が考えられます。
・中耳炎・耳管狭窄症:風邪などをきっかけに中耳や耳管に異常が起こると、低い音の耳鳴りが発生することがあります。耳がふさがったような感覚(耳閉感)を伴うことが多いです。
・滲出性中耳炎:中耳に液体が溜まることで音の伝わりが悪くなり、低い音の耳鳴りが起こることがあります。
・メニエール病:患者によっては高音ではなく「ブーン」「ザー」というような低い音の耳鳴りが起きることもあります。
・低音障害型感音難聴:低い音だけが聞こえにくくなる難聴で、低音の耳鳴りを伴います。めまい症状がないのが特徴で、ストレスや疲労により繰り返し起こることがあります。
・肩・首の凝り、疲労・ストレス:肩や首の凝りが原因で血行が悪くなり、低い音の耳鳴りが起こることがあります。
・急な気圧の変化:天候の変化で気圧が急に低下した時などに、低い音の耳鳴りが起こることがあります。
その他のタイプの耳鳴り
不定期に聞こえる耳鳴り(「ブクブク」「ポコポコ」「グググ」など)は、耳の周りの筋肉や耳小骨の筋肉がけいれんすることで発生することがあります。
乾いた音の耳鳴り(「ガサガサ」「ゴソゴソ」)は、耳垢が溜まっていたり、耳に虫が入ったりした場合に聞こえることがあります。
持続する拍動性の耳鳴り(「シャー」「ジョー」「ドクドク」など)は、脳と繋がっている血管に異常が起きている可能性があります。特に心臓の鼓動と同期している拍動性の耳鳴りは、脳梗塞や脳出血の前兆、脳腫瘍による血管の圧迫など重大な疾患の可能性もあるため注意が必要です。
片耳だけ耳鳴りがする原因は?
片耳だけに耳鳴りが発生する場合、特定の疾患や状態が関係している可能性があります。片耳の耳鳴りで考えられる主な原因は以下の通りです。
・突発性難聴:片側の耳に突然発症し、耳鳴りと聴力低下を伴います。早期治療が重要で、治療が遅れると元の聴力が戻りにくくなります。
・メニエール病:片側の耳に症状が出ることが多く、めまいや難聴と共に耳鳴りを伴います。進行すると両耳に症状が現れることもあります。
・聴神経腫瘍:片側の耳の聴神経に発生する良性腫瘍で、その側の耳に難聴と耳鳴りが起こります。
・ヘッドホン難聴:イヤホンやヘッドホンで大きな音を長時間聞き続けることで、片側または片側が強い形で耳鳴りが発生することがあります。
・耳垢栓塞:片方の耳に耳垢が詰まることで、その側に耳鳴りが起こることがあります。
・外傷:頭部や耳への外傷により、片側だけに耳鳴りが発生することがあります。
片耳だけの耳鳴りの場合、重大な疾患の可能性も否定できないため、早めに耳鼻咽喉科を受診して適切な検査を受けることが重要です。特にめまいや難聴を伴う場合や、症状が急に始まった場合は早急な医療機関の受診が必要です。
耳鳴りの検査方法
耳鳴りの原因を特定するためには、以下のような検査が行われます。
詳しい問診
医師は以下のような点について詳しく聞き取りを行います。
・耳鳴りの音の種類(高音か低音か、持続的か断続的かなど)
・いつから症状があるか
・片側か両側か
・耳鳴り以外の症状(難聴、めまい、耳の痛みなど)
・生活環境や仕事環境(騒音環境での就労歴など)
・服用中の薬剤
問診は耳鳴りの原因を探る上で非常に重要です。耳鳴りは自分にしか聞こえない「自覚的耳鳴り」が多いため、症状の詳細な聞き取りが診断の手がかりとなります。
聴力検査
聴力検査では、耳の聞こえ具合を調べるほか、以下のような検査が行われることがあります。
・純音聴力検査:さまざまな高さ(周波数)の純音をどの程度の大きさで聞き取れるかを調べます
・鼓膜の検査(ティンパノメトリー):鼓膜の動きや中耳の状態を調べます
・耳小骨筋反射検査:耳の奥の筋肉の動きを見る検査です
耳鳴検査
聴力検査機器(オージオメータ)を用いて、患者の耳鳴りの音に近い高さや強さ、音の種類などを調べます。これにより、耳鳴りの客観的な評価ができます。
画像検査
拍動性の耳鳴りの場合や、聴神経腫瘍などが疑われる場合には、以下のような画像検査が行われることがあります。
・MRI検査:脳の断面図を撮影します
・MRA検査:脳血管を立体画像化する検査です
その他、患者の状態に応じて血液検査や平衡機能検査(めまいがある場合)を行うこともあります。これらの検査結果を総合的に判断して、耳鳴りの原因を特定していきます。
耳鳴りの治し方
耳鳴りの治療法は原因によって異なります。基本的には原因となる疾患の治療が中心ですが、原因不明の耳鳴りに対する対処法も存在します。
医療機関での治療
耳鳴りの原因となる疾患が特定できた場合は、その疾患に対する治療を行います。
・薬物療法:ステロイド製剤、血管拡張剤、内耳の循環改善剤、ビタミン剤、抗不安剤、抗けいれん薬、漢方薬などが使用されます。特に突発性難聴では早期のステロイド治療が重要です。
・音響療法(TRT療法):耳鳴りと似た音や自然の音(波の音や小川のせせらぎなど)を聞くことで意識を分散させ、耳鳴りに対する意識をそらして慣らしていく治療法です。
・カウンセリング:耳鳴りによるストレスや不安を軽減するため、医師が詳しい説明を行い、患者の理解を促します(指示的カウンセリング)。
・認知行動療法:耳鳴りに対する考え方を変え、「少しくらい耳鳴りを感じても、普通に生活できている」という認識ができるように支援します。
・補聴器の使用:難聴を伴う耳鳴りの場合、補聴器を使用することで聞こえを改善し、それに伴い耳鳴りも軽減することがあります。
・手術:聴神経腫瘍や滲出性中耳炎など、病気によっては外科手術が必要になる場合もあります。
日常生活での対策
医療機関での治療と並行して、以下のような日常生活での対策も有効です。
夜間に耳鳴りが気になって眠れない場合は、小さな音量でテレビやラジオをつけたままにするなどの工夫も有効です。ただし、あまり大きな音だと逆効果になるため注意が必要です。
耳鳴りの鍼灸治療
東洋医学からみた耳鳴り
東洋医学では、耳鳴りは五臓六腑の「腎」と深い関わりがあるとされています。「腎は耳に開竅する」といわれ、腎の病変は耳に現れやすいと考えられています。
東洋医学における「腎」は西洋医学の腎臓とは異なり、主に生長・発育・生殖・水液代謝を司る役割を持っています。特に「腎の精気」は聴覚と関係が深く、精気が多ければ聴覚機能は正常に働き、少なければ聴覚機能は減退するとされています。
また、「腎が水を主る」という役割も耳鳴りと密接な関係があります。この「水」は西洋医学ではリンパ液に相当し、耳鳴りは耳の中のリンパ液が関係していることが多いことから、腎の機能低下により「水を主る」機能が減退していると考えられています。
鍼灸治療のアプローチ
耳鳴りに対する鍼灸治療は、以下のような段階的アプローチで行われることが多いです。
・自律神経の調整治療:耳鳴りに悩む人の多くは交感神経が過剰に活性化している状態にあります。鍼灸治療により交感神経を抑制し、副交感神経の働きを促進することで自律神経のバランスを整えます。
・背部や腎経へのアプローチ:背部のツボ(背部兪穴)を用いて「腎気」を補い、頸肩部の筋緊張を緩めます。耳鳴りがある人は耳裏から胸骨・鎖骨に伸びる胸鎖乳突筋の緊張が強い場合があるため、これらをほぐすことも重要です。
・耳周りへの治療:自律神経が整い、腎気を補い、頸肩部の筋緊張がほぐれた段階で耳周りの治療を行います。
鍼灸治療の効果は個人差がありますが、早期に治療を始めるほど効果が現れやすいとされています。低音の耳鳴りは比較的治りやすく、高音で持続的な耳鳴りは治療に時間がかかる傾向があります。
鳴りに即効性があるツボは?
耳鳴りを和らげるために効果的なツボがいくつかあります。これらを優しく刺激することで、耳周辺の血流を改善し、症状の緩和が期待できます。
特に効果が期待できる主なツボは以下の通りです。
・翳風(えいふう):耳の後ろにあるツボで、耳たぶの後ろにあるくぼみにあります。耳鳴りやめまいの緩和に効果があるとされています。
・聴宮(ちょうきゅう):耳穴の前にあるツボで、耳の付け根のほぼ中央に位置します。聴力を改善し、耳鳴りを和らげる効果があるとされています。
・耳門(じもん):耳の付け根の上にあるツボで、聴宮の指1本程度上が目安です。耳の不調全般に効果があります。
・完骨(かんこつ):耳の後ろにある出っ張った骨の下にあるくぼんだ部分にあります。耳鳴りやめまいの改善に効果があるとされています。
・百会(ひゃくえ):頭頂部に指を当てたときに、自然にくぼんでいる部分にあります。頭部の血流を改善する効果があります。
・風池(ふうち):首の後ろにある2本の筋肉のうち、外側にあるくぼんだ部分にあります。頭部と耳の血液循環を促進する効果があります。
ツボ押しをする際は、力を入れずにゆっくりと優しく円を描くように行いましょう。痛みを感じるほど強く押す必要はなく、心地よい刺激を与える程度で効果があります。
ただし、ツボ押しは対症療法的な効果が中心であり、根本的な原因治療ではありません。
症状が続く場合や強い場合は、医療機関での適切な診断と治療を受けることが重要です。また、拍動性の耳鳴りがある場合は、重大な疾患の可能性もあるため、早めに医療機関を受診しましょう。
お気軽にご相談ください
当院では、眼底出血の患者さまの症状や状態を総合的に評価し、最適な治療プランを提供します。鍼灸治療を含むさまざまなアプローチを用いて、患者さまの症状の緩和や生活の質の向上に努めます。専門的な知識と経験豊富なスタッフが、患者さまの健康をサポートします。まずはお気軽にご相談ください。
その他の対象疾患
-
眼科系
- VDT症候群
- アレルギー結膜炎
- シェーグレン症候群
- ドライアイ
- バセドウ病眼症
- ぶどう膜炎
- ポスナーシュロスマン症候群
- ホルネル症候群
- レーベル病
- 遠視
- 黄斑ジストロフィ
- 黄斑変性
- 黄班円孔
- 加齢黄斑変性
- 外傷性散瞳
- 外転神経麻痺
- 角膜ヘルペス
- 角膜炎
- 角膜潰瘍
- 角膜内皮障害
- 滑車神経麻痺
- 眼球振盪(眼振)
- 眼球突出症
- 眼筋ミオパチー
- 眼精疲労
- 眼痛
- 眼底出血
- 眼瞼下垂症
- 球後視神経炎
- 逆まつげ
- 強膜炎
- 近視
- 結膜弛緩症
- 原田病
- 交感性眼炎
- 光視症
- 蚕食性角膜潰瘍
- 視神経萎縮
- 視神経炎
- 視神経症
- 斜視
- 弱視
- 硝子体出血
- 硝子体剥離
- 色覚異常
- 増殖性硝子体網膜
- 中心性漿液性網脈絡膜症
- 糖尿病網膜症
- 虹彩毛様体炎
- 白内障
- 飛蚊症
- 複視
- 未熟児網膜症
- 網膜色素変性症
- 網膜静脈閉塞
- 網膜前黄斑線維症
- 網膜剥離
- 乱視
- 緑内障
- 歪視症
-
神経・精神系
- アルツハイマー病
- うつ病
- オリーブ橋小脳萎縮症
- くも膜下出血
- ジスキネジア
- ジストニア
- シャイドレーガー
- しゃっくり
- トロサハント症候群
- ナルコレプシー
- パーキンソン病
- パーキンソン症候群
- バーンアウト症候群
- パニック症候群
- ハンチントン病
- ハント症候群
- フリードライヒ
- ベル麻痺
- マシャド・ジョセフ病
- むずむず脚症候群
- メージュ症候群
- めまい(眩暈)
- モヤモヤ病
- 運動ニューロン病
- 延髄梗塞
- 下垂足
- 過食症
- 過食嘔吐
- 過敏性腸症候群
- 過眠症
- 眼瞼痙攣
- 顔面神経麻痺
- 顔面痛
- 記憶障害
- 起立性調節障害
- 起立性低血圧
- 球脊髄性筋萎縮症
- 拒食症
- 強迫性障害
- 恐怖症
- 胸髄損傷
- 筋ジストロフィー
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- 緊張性頭痛
- 群発頭痛
- 潔癖症
- 幻聴
- 減圧症
- 後頭神経痛
- 腰髄損傷
- 坐骨神経痛
- 三叉神経痛
- 視床出血後遺症
- 歯状核赤核淡蒼球ルイ体萎縮症
- 自律神経失調症
- 失語症
- 社会不安障害
- 重症筋無力症
- 小脳梗塞
- 小脳失調症
- 心身症
- 振戦
- 神経痛
- 神経麻痺
- 進行性核上性麻痺
- 水頭症
- 脊髄空洞症
- 脊髄梗塞
- 脊髄小脳変性症
- 脊髄性筋萎縮症
- 脊髄損傷
- 摂食障害
- 舌咽神経痛
- 線条体黒質変性症
- 前脊髄動脈症候群
- 双極性障害
- 多系統萎縮症
- 多発神経炎
- 多発性硬化症
- 体位性頻脈症候群
- 大脳皮質基底核変性
- 遅発ジスキネジア
- 統合失調症
- 頭痛
- 動眼神経麻痺
- 認知症(痴呆)
- 脳幹梗塞
- 脳幹出血
- 脳梗塞
- 脳梗塞後遺症
- 脳腫瘍
- 脳出血後遺症
- 脳脊髄液減少症
- 脳卒中後遺症
- 脳動脈解離
- 馬尾神経損傷
- 排尿障害
- 排便障害
- 反回神経麻痺
- 不随意運動
- 不眠症
- 片側顔面痙攣
- 片頭痛
- 片麻痺
- 本態性振戦
- 末梢神経障害
- 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
- 慢性疼痛
- 肋間神経痛
- 橈骨神経麻痺
- 痙性斜頸
- 痙攣性発声障害
- 癲癇
- 腓骨神経麻痺
- 頸髄損傷
-
整形外科系
- アキレス腱炎
- アキレス腱滑液包炎
- イップス
- ぎっくり腰
- すべり症
- ばね指
- ペルテス病
- リウマチ
- 乾癬性関節炎
- 関節炎
- 強直性脊椎炎
- 狭窄性腱鞘炎
- 胸郭出口症候群
- 頚椎間板ヘルニア
- 月状骨軟化症
- 肩こり
- 五十肩
- 後縦靭帯骨化症
- 広範腰脊柱管狭窄
- 腰椎間板ヘルニア
- 腰痛
- 骨粗鬆症
- 骨端症(骨端炎)
- 骨軟化症
- 尺骨神経麻痺
- 手根管症候群
- 手足の痛み
- 周期性四肢麻痺
- 書痙
- 寝違え
- 脊柱管狭窄症
- 脊柱側彎症
- 脊椎過敏症
- 脊椎分離症
- 線維筋痛症候群
- 足根管症候群
- 特発性ジストニア
- 背中の痛み
- 膝痛
- 肘部管症候群
- 変形性腰椎症
- 変形性膝関節症
- 変形性頸椎症
- 梨状筋症候群
- 腱鞘炎
- 頸肩腕症候群
- 頸部脊柱管狭窄症