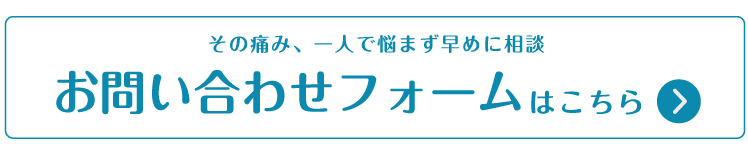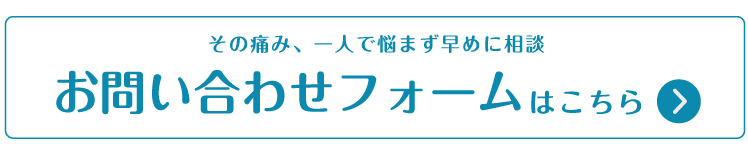好酸球性副鼻腔炎

好酸球性副鼻腔炎の症状
好酸球性副鼻腔炎は両側の鼻に多発性の鼻茸(ポリープ)が生じ、粘稠な鼻汁を特徴とする難治性の慢性副鼻腔炎です。一般的な副鼻腔炎とは異なり、抗生物質が効きにくく、手術をしても再発しやすいという特徴があります。
この疾患の主な症状には以下のようなものがあります。
・高度の鼻閉(鼻づまり)
・嗅覚障害(においがわからなくなる)
・粘り気の強い鼻汁
・口呼吸による口の渇きや喉の痛み
症状が進行すると、嗅覚は完全に消失することもあります。においがわからなくなることで食べ物の風味も感じにくくなり、味覚障害を引き起こします。鼻がつまることで口呼吸になり、口の渇きや喉の痛みを感じることも多いです。
好酸球性副鼻腔炎は他の疾患を合併することがあり、特に気管支喘息やアスピリン不耐症(NSAIDs不耐症)、好酸球性中耳炎などとの関連が強いとされています。好酸球性中耳炎を合併すると、耳だれや難聴などの症状も現れます。耳だれも鼻汁と同様に粘り気が強く、止めることが難しいという特徴があります。
血液検査では好酸球の数値が高くなっていることが多く、CTでは目と目の間の部分(篩骨洞)に濃い陰影が見られることが特徴的です。好酸球性副鼻腔炎は一度発症すると、繰り返し症状が悪化と軽快を繰り返す難治性の疾患で、2015年に特定疾患(難病)に指定されています。
好酸球性副鼻腔炎の原因
好酸球性副鼻腔炎の明確な原因はまだ解明されていませんが、いくつかの要因が関連していると考えられています。
主な特徴は、鼻粘膜に好酸球という免疫細胞が多数集積することです。好酸球は通常、寄生虫感染などに対する防御機能を持っていますが、この疾患では過剰に反応して炎症を引き起こしていると考えられています。特に、Type 2炎症と呼ばれる免疫反応が主体となっており、IL-4やIL-13といった物質が重要な役割を担っています。
好酸球性副鼻腔炎の発症や悪化に関連する要因としては以下のようなものがあります。
・免疫系の異常反応(好酸球の過剰集積)
・全身性の呼吸器疾患との関連(気管支喘息など)
・ウイルス感染の影響
・環境要因や遺伝的要因
この疾患が1990年代後半から増加し始めた背景には、重症の気管支喘息治療の変化との関連が指摘されています。それまでは経口ステロイドが使用されていましたが、吸入ステロイドが主流になった時期と好酸球性副鼻腔炎の増加時期が一致しています。これは、経口ステロイドが好酸球性副鼻腔炎の症状も抑えていた可能性を示唆しています。
また、鼻茸の組織では血液を固める作用が亢進し、血の塊を溶かす作用が減弱していることもわかっています。そのため、フィブリンと呼ばれるタンパク質が沈着しやすくなっています。
この疾患は主に成人(20歳以上)で発症し、15歳以下の子供ではほとんど見られません。また、男性の方が女性よりも多い傾向があり、平均発症年齢は50~55歳とされています。日本では約100万〜200万人いる副鼻腔炎患者のうち、鼻茸がある慢性副鼻腔炎患者は約20万人、そのうち好酸球性副鼻腔炎の中等症・重症患者は約2万人と推定されています。
好酸球性副鼻腔炎の改善方法
好酸球性副鼻腔炎の改善には、主に薬物療法と手術療法があります。しかし、完全に治すことは難しく、症状のコントロールが主な目標となります。
薬物療法の中心となるのはステロイド薬です。好酸球性副鼻腔炎の主な治療法には以下のようなものがあります。
・経口ステロイド(最も効果的だが副作用のリスクあり)
・抗生物質(細菌感染による症状悪化の防止)
・生物学的製剤(抗IL-4/13受容体抗体など)
経口ステロイドは最も効果的な治療法で、鼻茸を縮小させ、鼻づまりや嗅覚障害を改善します。通常、約3か月間かけて少しずつ量を減らしながら使用しますが、長期間の使用は様々な副作用を引き起こす可能性があるため、症状が軽快したら一旦中止するのが一般的です。
鼻茸が大きくなり、薬物療法だけでは症状をコントロールできない場合は、手術療法が検討されます。内視鏡下鼻内副鼻腔手術により鼻茸を完全に取り除くことで、一時的に鼻づまりは解消されますが、多くの場合、時間の経過とともに鼻茸は再発します。手術後は鼻の洗浄とステロイドの使用を組み合わせながら、鼻の状態を定期的に観察することが重要です。
一部の医療機関では、以下のような特殊な治療も行われています。
・鼻腔局所ステロイド治療
・自己血清点眼
好酸球性副鼻腔炎の治療において完全な治癒は難しく、多くの場合、症状の緩和と再発の予防が主な目標となります。軽症から重症を含めて、内視鏡下鼻内副鼻腔手術を行った場合、術後6年間で50%の症例が再発するとされており、特にアスピリン喘息に伴う好酸球性副鼻腔炎では、術後4年以内に全例が再発するとの報告もあります。
好酸球性副鼻腔炎の鍼灸治療・ツボ
好酸球性副鼻腔炎は西洋医学的には難治性疾患とされていますが、東洋医学的アプローチである鍼灸治療が症状改善に効果を示した症例が報告されています。鍼灸治療では、病名だけでなく患者の体質や症状に合わせた全体的なアプローチを行います。
東洋医学的な考え方
東洋医学では、好酸球性副鼻腔炎は以下のような病態として捉えられています。
・気血津液の不足
・痰湿お血鬱阻(たんしつおけつうっそ)
・久病による気血津液不足
鍼灸治療では、これらの状態を改善するために、不足した気血津液を補い、滞っている鼻周辺の気血の巡りを改善することを目指します。
効果的なツボと鍼灸施術
好酸球性副鼻腔炎に効果的とされる主なツボには以下のようなものがあります。
・天迎香(てんげいこう):鼻翼の外側
・鼻通(びつう):小鼻のすぐ横
・印堂(いんどう):眉間の真ん中
・内関(ないかん):手首の内側
・血海(けっかい):膝の内側
・三陰交(さんいんこう):足首の内側
これらのツボは、鼻水や鼻詰まりの改善、ストレスや緊張の緩和、自律神経のバランス調整、血の巡りの改善、全身の気血の調整などの効果があるとされています。特に印堂は嗅覚神経中枢に近いため、嗅覚障害の改善にも効果が期待できます。
鍼灸治療では、まず鼻周辺のツボを中心に局所の血流を改善し、炎症を抑えることを目指す局所的アプローチを行います。また、全身の気血のバランスを整えることで免疫系の正常化を促す全身的アプローチも重要です。さらに、より効果的な治療のために、鍼灸治療と漢方薬(釣藤散など)を併用するケースも多いです。
実際の臨床例では、鍼灸治療と漢方薬の併用により、嗅覚と味覚の改善、鼻づまりの軽減、さらに血液検査で好酸球数の減少が確認された症例も報告されています。ただし、効果の現れ方や程度には個人差があり、継続的な治療が必要な場合が多いです。
好酸球性副鼻腔炎に対する鍼灸治療のメリット
好酸球性副鼻腔炎に対する鍼灸治療には、西洋医学的な治療と比較していくつかの特徴的なメリットがあります。
鍼灸治療の主なメリットには以下のようなものがあります。
・体質改善と根本的なアプローチが可能
・副作用のリスクが少ない
・合併症や関連症状にも効果が期待できる
・個別化された治療アプローチが可能
鍼灸治療の最大のメリットは、単に症状を抑えるだけでなく、体質改善を通じて根本的な原因にアプローチするという点です。東洋医学では病気を局所的な問題ではなく、全身のバランスの崩れとして捉えます。鍼灸治療により気血津液のバランスを整えることで、免疫系の過剰反応を調整し、好酸球性副鼻腔炎の根本的な病態改善を目指します。
また、鍼灸治療は自律神経系を調整することで、間接的に免疫系にも作用し、好酸球の過剰な活性化を抑制する可能性があります。実際に、鍼灸治療後に血中好酸球数が減少した症例も報告されています。さらに、鼻周辺や全身の血行を促進することで、鼻茸の縮小や鼻粘膜の正常化を促す効果も期待できます。
好酸球性副鼻腔炎の西洋医学的治療の中心となるステロイド薬は、長期使用による様々な副作用が懸念されますが、鍼灸治療にはそのような重大な副作用がなく、長期的に継続しても安全性が高いという特徴があります。体内の自然治癒力を高める治療法であるため、外部から薬物を投与する治療法と比べて身体への負担が少ないと考えられています。
実際の臨床例では、数か月間の継続的な鍼灸治療と漢方薬の併用により、嗅覚テストのスコアが大幅に改善したケースや、血中好酸球数が減少したケースが報告されています。これらは、好酸球性副鼻腔炎に対する鍼灸治療の可能性を示す重要な事例と言えるでしょう。
好酸球性副鼻腔炎に対する鍼灸治療のデメリット
鍼灸治療は好酸球性副鼻腔炎に対して様々なメリットがありますが、いくつかの限界やデメリットも存在します。治療を検討する際には、これらの点も理解しておくことが重要です。
鍼灸治療の主なデメリットには以下のようなものがあります。
・効果発現までの時間がかかる
・個人差と効果の予測困難性がある
・施術者の技術と経験による差がある
・西洋医学的治療との関係(補完的役割)
鍼灸治療の効果は徐々に現れることが多く、即効性については制限があります。好酸球性副鼻腔炎のような慢性的な炎症状態では、鍼灸治療の効果が現れるまでに時間がかかることがあり、症例報告によれば、多くの場合、明確な改善を実感するまでに数回から数十回の治療が必要です。また、風邪などをきっかけに症状が急激に悪化した場合、鍼灸治療だけでは十分な即時効果が得られないこともあります。
さらに、鍼灸治療の効果には個人差があり、全ての患者に同様の効果が得られるわけではありません。同じ症状を持つ患者でも、体質や病態の違いにより鍼灸治療への反応は異なります。特に長期間罹患している重症例では効果が現れにくいことがあります。また、治療を始める前に、その効果を正確に予測することは困難であり、一定期間治療を受けてみないと効果があるかどうかわからない場合があります。
鍼灸治療の効果は施術者の技術や経験に大きく依存します。好酸球性副鼻腔炎に対する鍼灸治療は、単なる対症療法ではなく、病態生理を理解した上での総合的なアプローチが必要です。そのため、この疾患に精通した鍼灸師を見つけることが重要ですが、同じツボを使用しても、刺激方法や強さ、時間などによって効果は異なり、熟練した施術者と経験の浅い施術者では治療効果に差が出ることがあります。
重症の好酸球性副鼻腔炎では、鍼灸治療だけでは症状のコントロールが難しい場合があります。特に鼻茸が大きく鼻腔をほぼ閉塞しているような状態では、手術による物理的な除去が必要になることもあります。鍼灸治療は西洋医学的治療の代替というよりも、補完的な役割が適していることが多いです。
普段からできるドライアイの予防法
好酸球性副鼻腔炎は繰り返し再発しやすい疾患ですが、日常生活での心がけによって症状の悪化を防いだり、再発のリスクを軽減したりすることができます。以下に、日常生活で実践できる予防法を紹介します。
感染予防は特に重要です。好酸球性副鼻腔炎は風邪などの感染をきっかけに症状が悪化することが多いため、以下のような対策が効果的です。
・手洗い・うがいの習慣化
・マスクの着用(特に花粉の時期や風邪の流行期)
・適切な湿度の維持(加湿器の使用など)
規則正しい生活習慣も免疫力の維持に役立ち、症状の安定に寄与します。
・十分な睡眠
・バランスの取れた食事
・適度な運動
・水分摂取
ストレスは免疫バランスを崩し、症状の悪化につながる可能性があるため、ストレス管理も重要です。
・ストレス解消法の実践
・無理のない生活設計
・リラクゼーション技法の取り入れ
また、アレルゲンを避けるなどの環境への配慮も大切です。
・アレルゲンの回避(特にアスピリンなどのNSAIDs)
・室内環境の整備(定期的な掃除や換気)
・大気汚染の回避
自宅でできるケアとしては、医師に相談した上での鼻洗浄や、蒸気吸入、首や顔の周りを温めること、ツボ押しなどがあります。
定期的な医療機関への受診も重要です。症状が安定していても、定期的に耳鼻科を受診し、鼻の状態を確認してもらいましょう。医師から処方された薬は指示通りに継続して使用し、症状の変化をメモしておくと、医師への報告や自己管理に役立ちます。また、症状の悪化を感じたら、早めに医療機関を受診することが大切です。
好酸球性副鼻腔炎は慢性疾患であり、完全に予防することは難しいかもしれませんが、これらの日常的な対策を継続して行うことで、症状の安定や悪化の予防、生活の質の向上につながりま
好酸球性副鼻腔炎は両側の鼻に多発性の鼻茸(ポリープ)が生じ、粘稠な鼻汁を特徴とする難治性の慢性副鼻腔炎です。一般的な副鼻腔炎とは異なり、抗生物質が効きにくく、手術をしても再発しやすいという特徴があります。
この疾患の主な症状には以下のようなものがあります。
・高度の鼻閉(鼻づまり)
・嗅覚障害(においがわからなくなる)
・粘り気の強い鼻汁
・口呼吸による口の渇きや喉の痛み
症状が進行すると、嗅覚は完全に消失することもあります。においがわからなくなることで食べ物の風味も感じにくくなり、味覚障害を引き起こします。鼻がつまることで口呼吸になり、口の渇きや喉の痛みを感じることも多いです。
好酸球性副鼻腔炎は他の疾患を合併することがあり、特に気管支喘息やアスピリン不耐症(NSAIDs不耐症)、好酸球性中耳炎などとの関連が強いとされています。好酸球性中耳炎を合併すると、耳だれや難聴などの症状も現れます。耳だれも鼻汁と同様に粘り気が強く、止めることが難しいという特徴があります。
血液検査では好酸球の数値が高くなっていることが多く、CTでは目と目の間の部分(篩骨洞)に濃い陰影が見られることが特徴的です。好酸球性副鼻腔炎は一度発症すると、繰り返し症状が悪化と軽快を繰り返す難治性の疾患で、2015年に特定疾患(難病)に指定されています。
好酸球性副鼻腔炎の原因
好酸球性副鼻腔炎の明確な原因はまだ解明されていませんが、いくつかの要因が関連していると考えられています。
主な特徴は、鼻粘膜に好酸球という免疫細胞が多数集積することです。好酸球は通常、寄生虫感染などに対する防御機能を持っていますが、この疾患では過剰に反応して炎症を引き起こしていると考えられています。特に、Type 2炎症と呼ばれる免疫反応が主体となっており、IL-4やIL-13といった物質が重要な役割を担っています。
好酸球性副鼻腔炎の発症や悪化に関連する要因としては以下のようなものがあります。
・免疫系の異常反応(好酸球の過剰集積)
・全身性の呼吸器疾患との関連(気管支喘息など)
・ウイルス感染の影響
・環境要因や遺伝的要因
この疾患が1990年代後半から増加し始めた背景には、重症の気管支喘息治療の変化との関連が指摘されています。それまでは経口ステロイドが使用されていましたが、吸入ステロイドが主流になった時期と好酸球性副鼻腔炎の増加時期が一致しています。これは、経口ステロイドが好酸球性副鼻腔炎の症状も抑えていた可能性を示唆しています。
また、鼻茸の組織では血液を固める作用が亢進し、血の塊を溶かす作用が減弱していることもわかっています。そのため、フィブリンと呼ばれるタンパク質が沈着しやすくなっています。
この疾患は主に成人(20歳以上)で発症し、15歳以下の子供ではほとんど見られません。また、男性の方が女性よりも多い傾向があり、平均発症年齢は50~55歳とされています。日本では約100万〜200万人いる副鼻腔炎患者のうち、鼻茸がある慢性副鼻腔炎患者は約20万人、そのうち好酸球性副鼻腔炎の中等症・重症患者は約2万人と推定されています。
好酸球性副鼻腔炎の改善方法
好酸球性副鼻腔炎の改善には、主に薬物療法と手術療法があります。しかし、完全に治すことは難しく、症状のコントロールが主な目標となります。
薬物療法の中心となるのはステロイド薬です。好酸球性副鼻腔炎の主な治療法には以下のようなものがあります。
・経口ステロイド(最も効果的だが副作用のリスクあり)
・抗生物質(細菌感染による症状悪化の防止)
・生物学的製剤(抗IL-4/13受容体抗体など)
経口ステロイドは最も効果的な治療法で、鼻茸を縮小させ、鼻づまりや嗅覚障害を改善します。通常、約3か月間かけて少しずつ量を減らしながら使用しますが、長期間の使用は様々な副作用を引き起こす可能性があるため、症状が軽快したら一旦中止するのが一般的です。
鼻茸が大きくなり、薬物療法だけでは症状をコントロールできない場合は、手術療法が検討されます。内視鏡下鼻内副鼻腔手術により鼻茸を完全に取り除くことで、一時的に鼻づまりは解消されますが、多くの場合、時間の経過とともに鼻茸は再発します。手術後は鼻の洗浄とステロイドの使用を組み合わせながら、鼻の状態を定期的に観察することが重要です。
一部の医療機関では、以下のような特殊な治療も行われています。
・鼻腔局所ステロイド治療
・自己血清点眼
好酸球性副鼻腔炎の治療において完全な治癒は難しく、多くの場合、症状の緩和と再発の予防が主な目標となります。軽症から重症を含めて、内視鏡下鼻内副鼻腔手術を行った場合、術後6年間で50%の症例が再発するとされており、特にアスピリン喘息に伴う好酸球性副鼻腔炎では、術後4年以内に全例が再発するとの報告もあります。
好酸球性副鼻腔炎の鍼灸治療・ツボ
好酸球性副鼻腔炎は西洋医学的には難治性疾患とされていますが、東洋医学的アプローチである鍼灸治療が症状改善に効果を示した症例が報告されています。鍼灸治療では、病名だけでなく患者の体質や症状に合わせた全体的なアプローチを行います。
東洋医学的な考え方
東洋医学では、好酸球性副鼻腔炎は以下のような病態として捉えられています。
・気血津液の不足
・痰湿お血鬱阻(たんしつおけつうっそ)
・久病による気血津液不足
鍼灸治療では、これらの状態を改善するために、不足した気血津液を補い、滞っている鼻周辺の気血の巡りを改善することを目指します。
効果的なツボと鍼灸施術
好酸球性副鼻腔炎に効果的とされる主なツボには以下のようなものがあります。
・天迎香(てんげいこう):鼻翼の外側
・鼻通(びつう):小鼻のすぐ横
・印堂(いんどう):眉間の真ん中
・内関(ないかん):手首の内側
・血海(けっかい):膝の内側
・三陰交(さんいんこう):足首の内側
これらのツボは、鼻水や鼻詰まりの改善、ストレスや緊張の緩和、自律神経のバランス調整、血の巡りの改善、全身の気血の調整などの効果があるとされています。特に印堂は嗅覚神経中枢に近いため、嗅覚障害の改善にも効果が期待できます。
鍼灸治療では、まず鼻周辺のツボを中心に局所の血流を改善し、炎症を抑えることを目指す局所的アプローチを行います。また、全身の気血のバランスを整えることで免疫系の正常化を促す全身的アプローチも重要です。さらに、より効果的な治療のために、鍼灸治療と漢方薬(釣藤散など)を併用するケースも多いです。
実際の臨床例では、鍼灸治療と漢方薬の併用により、嗅覚と味覚の改善、鼻づまりの軽減、さらに血液検査で好酸球数の減少が確認された症例も報告されています。ただし、効果の現れ方や程度には個人差があり、継続的な治療が必要な場合が多いです。
好酸球性副鼻腔炎に対する鍼灸治療のメリット
好酸球性副鼻腔炎に対する鍼灸治療には、西洋医学的な治療と比較していくつかの特徴的なメリットがあります。
鍼灸治療の主なメリットには以下のようなものがあります。
・体質改善と根本的なアプローチが可能
・副作用のリスクが少ない
・合併症や関連症状にも効果が期待できる
・個別化された治療アプローチが可能
鍼灸治療の最大のメリットは、単に症状を抑えるだけでなく、体質改善を通じて根本的な原因にアプローチするという点です。東洋医学では病気を局所的な問題ではなく、全身のバランスの崩れとして捉えます。鍼灸治療により気血津液のバランスを整えることで、免疫系の過剰反応を調整し、好酸球性副鼻腔炎の根本的な病態改善を目指します。
また、鍼灸治療は自律神経系を調整することで、間接的に免疫系にも作用し、好酸球の過剰な活性化を抑制する可能性があります。実際に、鍼灸治療後に血中好酸球数が減少した症例も報告されています。さらに、鼻周辺や全身の血行を促進することで、鼻茸の縮小や鼻粘膜の正常化を促す効果も期待できます。
好酸球性副鼻腔炎の西洋医学的治療の中心となるステロイド薬は、長期使用による様々な副作用が懸念されますが、鍼灸治療にはそのような重大な副作用がなく、長期的に継続しても安全性が高いという特徴があります。体内の自然治癒力を高める治療法であるため、外部から薬物を投与する治療法と比べて身体への負担が少ないと考えられています。
実際の臨床例では、数か月間の継続的な鍼灸治療と漢方薬の併用により、嗅覚テストのスコアが大幅に改善したケースや、血中好酸球数が減少したケースが報告されています。これらは、好酸球性副鼻腔炎に対する鍼灸治療の可能性を示す重要な事例と言えるでしょう。
好酸球性副鼻腔炎に対する鍼灸治療のデメリット
鍼灸治療は好酸球性副鼻腔炎に対して様々なメリットがありますが、いくつかの限界やデメリットも存在します。治療を検討する際には、これらの点も理解しておくことが重要です。
鍼灸治療の主なデメリットには以下のようなものがあります。
・効果発現までの時間がかかる
・個人差と効果の予測困難性がある
・施術者の技術と経験による差がある
・西洋医学的治療との関係(補完的役割)
鍼灸治療の効果は徐々に現れることが多く、即効性については制限があります。好酸球性副鼻腔炎のような慢性的な炎症状態では、鍼灸治療の効果が現れるまでに時間がかかることがあり、症例報告によれば、多くの場合、明確な改善を実感するまでに数回から数十回の治療が必要です。また、風邪などをきっかけに症状が急激に悪化した場合、鍼灸治療だけでは十分な即時効果が得られないこともあります。
さらに、鍼灸治療の効果には個人差があり、全ての患者に同様の効果が得られるわけではありません。同じ症状を持つ患者でも、体質や病態の違いにより鍼灸治療への反応は異なります。特に長期間罹患している重症例では効果が現れにくいことがあります。また、治療を始める前に、その効果を正確に予測することは困難であり、一定期間治療を受けてみないと効果があるかどうかわからない場合があります。
鍼灸治療の効果は施術者の技術や経験に大きく依存します。好酸球性副鼻腔炎に対する鍼灸治療は、単なる対症療法ではなく、病態生理を理解した上での総合的なアプローチが必要です。そのため、この疾患に精通した鍼灸師を見つけることが重要ですが、同じツボを使用しても、刺激方法や強さ、時間などによって効果は異なり、熟練した施術者と経験の浅い施術者では治療効果に差が出ることがあります。
重症の好酸球性副鼻腔炎では、鍼灸治療だけでは症状のコントロールが難しい場合があります。特に鼻茸が大きく鼻腔をほぼ閉塞しているような状態では、手術による物理的な除去が必要になることもあります。鍼灸治療は西洋医学的治療の代替というよりも、補完的な役割が適していることが多いです。
普段からできるドライアイの予防法
好酸球性副鼻腔炎は繰り返し再発しやすい疾患ですが、日常生活での心がけによって症状の悪化を防いだり、再発のリスクを軽減したりすることができます。以下に、日常生活で実践できる予防法を紹介します。
感染予防は特に重要です。好酸球性副鼻腔炎は風邪などの感染をきっかけに症状が悪化することが多いため、以下のような対策が効果的です。
・手洗い・うがいの習慣化
・マスクの着用(特に花粉の時期や風邪の流行期)
・適切な湿度の維持(加湿器の使用など)
規則正しい生活習慣も免疫力の維持に役立ち、症状の安定に寄与します。
・十分な睡眠
・バランスの取れた食事
・適度な運動
・水分摂取
ストレスは免疫バランスを崩し、症状の悪化につながる可能性があるため、ストレス管理も重要です。
・ストレス解消法の実践
・無理のない生活設計
・リラクゼーション技法の取り入れ
また、アレルゲンを避けるなどの環境への配慮も大切です。
・アレルゲンの回避(特にアスピリンなどのNSAIDs)
・室内環境の整備(定期的な掃除や換気)
・大気汚染の回避
自宅でできるケアとしては、医師に相談した上での鼻洗浄や、蒸気吸入、首や顔の周りを温めること、ツボ押しなどがあります。
定期的な医療機関への受診も重要です。症状が安定していても、定期的に耳鼻科を受診し、鼻の状態を確認してもらいましょう。医師から処方された薬は指示通りに継続して使用し、症状の変化をメモしておくと、医師への報告や自己管理に役立ちます。また、症状の悪化を感じたら、早めに医療機関を受診することが大切です。
好酸球性副鼻腔炎は慢性疾患であり、完全に予防することは難しいかもしれませんが、これらの日常的な対策を継続して行うことで、症状の安定や悪化の予防、生活の質の向上につながります。
お気軽にご相談ください
当院では、好酸球性副鼻腔炎の患者さまの症状や状態を総合的に評価し、最適な治療プランを提供します。鍼灸治療を含むさまざまなアプローチを用いて、患者さまの症状の緩和や生活の質の向上に努めます。専門的な知識と経験豊富なスタッフが、患者さまの健康をサポートします。まずはお気軽にご相談ください。
その他の対象疾患
-
眼科系
- VDT症候群
- アレルギー結膜炎
- シェーグレン症候群
- ドライアイ
- バセドウ病眼症
- ぶどう膜炎
- ポスナーシュロスマン症候群
- ホルネル症候群
- レーベル病
- 遠視
- 黄斑ジストロフィ
- 黄斑変性
- 黄班円孔
- 加齢黄斑変性
- 外傷性散瞳
- 外転神経麻痺
- 角膜ヘルペス
- 角膜炎
- 角膜潰瘍
- 角膜内皮障害
- 滑車神経麻痺
- 眼球振盪(眼振)
- 眼球突出症
- 眼筋ミオパチー
- 眼精疲労
- 眼痛
- 眼底出血
- 眼瞼下垂症
- 球後視神経炎
- 逆まつげ
- 強膜炎
- 近視
- 結膜弛緩症
- 原田病
- 交感性眼炎
- 光視症
- 蚕食性角膜潰瘍
- 視神経萎縮
- 視神経炎
- 視神経症
- 斜視
- 弱視
- 硝子体出血
- 硝子体剥離
- 色覚異常
- 増殖性硝子体網膜
- 中心性漿液性網脈絡膜症
- 糖尿病網膜症
- 虹彩毛様体炎
- 白内障
- 飛蚊症
- 複視
- 未熟児網膜症
- 網膜色素変性症
- 網膜静脈閉塞
- 網膜前黄斑線維症
- 網膜剥離
- 乱視
- 緑内障
- 歪視症
-
神経・精神系
- アルツハイマー病
- うつ病
- オリーブ橋小脳萎縮症
- くも膜下出血
- ジスキネジア
- ジストニア
- シャイドレーガー
- しゃっくり
- トロサハント症候群
- ナルコレプシー
- パーキンソン病
- パーキンソン症候群
- バーンアウト症候群
- パニック症候群
- ハンチントン病
- ハント症候群
- フリードライヒ
- ベル麻痺
- マシャド・ジョセフ病
- むずむず脚症候群
- メージュ症候群
- めまい(眩暈)
- モヤモヤ病
- 運動ニューロン病
- 延髄梗塞
- 下垂足
- 過食症
- 過食嘔吐
- 過敏性腸症候群
- 過眠症
- 眼瞼痙攣
- 顔面神経麻痺
- 顔面痛
- 記憶障害
- 起立性調節障害
- 起立性低血圧
- 球脊髄性筋萎縮症
- 拒食症
- 強迫性障害
- 恐怖症
- 胸髄損傷
- 筋ジストロフィー
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- 緊張性頭痛
- 群発頭痛
- 潔癖症
- 幻聴
- 減圧症
- 後頭神経痛
- 腰髄損傷
- 坐骨神経痛
- 三叉神経痛
- 視床出血後遺症
- 歯状核赤核淡蒼球ルイ体萎縮症
- 自律神経失調症
- 失語症
- 社会不安障害
- 重症筋無力症
- 小脳梗塞
- 小脳失調症
- 心身症
- 振戦
- 神経痛
- 神経麻痺
- 進行性核上性麻痺
- 水頭症
- 脊髄空洞症
- 脊髄梗塞
- 脊髄小脳変性症
- 脊髄性筋萎縮症
- 脊髄損傷
- 摂食障害
- 舌咽神経痛
- 線条体黒質変性症
- 前脊髄動脈症候群
- 双極性障害
- 多系統萎縮症
- 多発神経炎
- 多発性硬化症
- 体位性頻脈症候群
- 大脳皮質基底核変性
- 遅発ジスキネジア
- 統合失調症
- 頭痛
- 動眼神経麻痺
- 認知症(痴呆)
- 脳幹梗塞
- 脳幹出血
- 脳梗塞
- 脳梗塞後遺症
- 脳腫瘍
- 脳出血後遺症
- 脳脊髄液減少症
- 脳卒中後遺症
- 脳動脈解離
- 馬尾神経損傷
- 排尿障害
- 排便障害
- 反回神経麻痺
- 不随意運動
- 不眠症
- 片側顔面痙攣
- 片頭痛
- 片麻痺
- 本態性振戦
- 末梢神経障害
- 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
- 慢性疼痛
- 肋間神経痛
- 橈骨神経麻痺
- 痙性斜頸
- 痙攣性発声障害
- 癲癇
- 腓骨神経麻痺
- 頸髄損傷
-
整形外科系
- アキレス腱炎
- アキレス腱滑液包炎
- イップス
- ぎっくり腰
- すべり症
- ばね指
- ペルテス病
- リウマチ
- 乾癬性関節炎
- 関節炎
- 強直性脊椎炎
- 狭窄性腱鞘炎
- 胸郭出口症候群
- 頚椎間板ヘルニア
- 月状骨軟化症
- 肩こり
- 五十肩
- 後縦靭帯骨化症
- 広範腰脊柱管狭窄
- 腰椎間板ヘルニア
- 腰痛
- 骨粗鬆症
- 骨端症(骨端炎)
- 骨軟化症
- 尺骨神経麻痺
- 手根管症候群
- 手足の痛み
- 周期性四肢麻痺
- 書痙
- 寝違え
- 脊柱管狭窄症
- 脊柱側彎症
- 脊椎過敏症
- 脊椎分離症
- 線維筋痛症候群
- 足根管症候群
- 特発性ジストニア
- 背中の痛み
- 膝痛
- 肘部管症候群
- 変形性腰椎症
- 変形性膝関節症
- 変形性頸椎症
- 梨状筋症候群
- 腱鞘炎
- 頸肩腕症候群
- 頸部脊柱管狭窄症